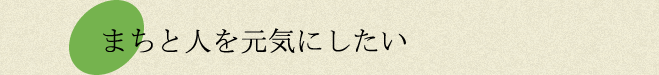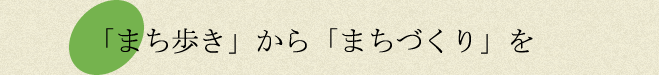市街地には城下町の趣を残した小路も多く、古い建物が情緒あふれるまちなみを彩っているが、現在では高齢化が進み、その多くが空き家になってしまった。
城下町洲本再生委員会会長の野口純子さんは、そんなレトロな雰囲気を活かして洲本のまちを再生しようと声を上げた住人の一人だ。
淡路島最後の映画館「洲本オリオン」の経営に携わりながら、かつての活気を失いつつある地域に元気を取り戻したいと活動を始めた。2年前に始めた「城下町洲本 レトロなまち歩き」は今春5回目を迎え、県内外から約70店が出店、1万人を超える人たちが訪れる大イベントに成長している。

淡路、洲本、南あわじの3つの市からなる淡路島。野口純子さんは、母の実家がある阿万町(現在の南あわじ市)に生まれ育ち、3歳の頃、洲本市に移り住んだ。
父は洋画の封切館「洲本オリオン」を経営していた。一人娘だった野口さんは、「映画館のお嬢さん」として何の苦労もなく成長したが、高校3年生の冬、突然父が他界。この時を境に、「映画館のお嬢さん」は館を切り盛りする経営者になった。
新しい映画の上映が決まるとポスターに刷毛で糊を塗り、電信柱に貼ってまわった。「風に吹かれたポスターが顔に張り付いて困った」と、無我夢中だった青春時代を懐かしそうに語る。
映画の全盛期だった昭和20年代、淡路島には17館もの映画館があった。そのうちの一つだった洲本オリオンも、250席の映画館として地域に親しまれていた。近所の人が普段の生活の中で映画を観るような時代、作詞家の阿久悠さんや俳優の笹野高史さんも常連客の一人だった。この頃、淡路にはオリオンが輝いていた。
ブームが下火になり、洲本オリオンは淡路島で唯一の映画館になった。それでも野口さんは、館内が一つになって笑い、泣く、そんな空間を共有できる映画の火を絶やしたくないと頑張り続けた。スクリーンに愛の言葉を映し出してプロポーズの場を提供したり、亡き父と通った映画館で息子と一緒に映画を観たいというお客さんのために家族だけの貸切上映をするなど、小さな映画館だからこそできることをやってきた。
昨年秋、止む無く休館することになったが、今も不定期の映画上映やコンサート、大衆演劇のホールとして活用している。

淡路島最後の映画館洲本オリオン(現在休館中)
そんな野口さんが地域活動に乗り出したのは、洲本オリオンのある市街地で急速に進む高齢化を何とかしなくてはという思いからだった。
地域の人たちがお互いに顔を合わせ、安心して暮らせるまちをつくりたいと、25年前に誕生したのが洲本市外町地区愛育班だ。野口さんは長くその班長として、昔ながらのご近所づきあいを土台とした支え合いの場づくりに取り組んできた。一人暮らしの高齢者を定期的に訪ねて声をかけ、見聞きしたことやその時の様子をメモして担当の保健師につなぐ「声掛けメモ」を作ったのも、そんな取り組みの一つだ。
一方で、まちの様子に目をやると、かつて華やかだった商店街は薄暗くひっそりとし、生活の匂いの漂っていた路地からは人の声が聞こえなくなってしまっている。
「まちの賑わいを取り戻すことで、地域の人たちを元気にしたい」
人を軸とした愛育班の活動が、まちの活性化という目標につながった。

和服でレトロなまち歩き
「自分たちの住むまちを何とかしたい」という思いを持っていたのは野口さんだけではなかった。2年前、志を同じくするメンバー約20名が、県民局職員の呼びかけをきっかけに集まった。その中には、大学卒業後に島へUターンしてきた若者も含まれていた。
その集まりでまちの活性化についてさまざまな意見が出された結果、「市街地のレトロな雰囲気を生かして地域おこしができるのではないか」という着想が生まれた。翌月、早速「城下町洲本再生委員会」が結成され、野口さんは会長に就任。若者がまちなかで過ごせる場所と仕事をつくり、まちに居住者を呼び戻すことを目標にした活動が動き始めた。
そうして最初の会議から4ヵ月というスピードで開催にこぎつけた「城下町洲本 レトロなまち歩き」。多くの人にまち歩きを楽しんでもらい、洲本の魅力に触れてもらうと同時に、現在空き家となっているところにアトリエショップやカフェなど魅力的な店舗を誘致することで、地域力を底上げすることも狙ったイベントになった。
平成24年4月、開催日の2日間限定で出店者を募ってスタートした第1回には、地域住民をはじめ県内外から70軒を超える出店者が集まる盛況ぶり。8,000人もの参加者でにぎわった。

イベント当日。洲本オリオンの前の賑わい

県立洲本高等学校ミュージックダンス部のパフォーマンス
第2回を終えた後の平成24年12月には、野口さん自身も築140年の建物を買い取り、「こみち食堂」を開店した。提供するのは地元の食材をふんだんに使った手づくり料理だ。栄養バランスを考えた健康メニューで、常連客も多い。食事のためだけに暖簾をくぐるのではなく、コミュニケーションを求めてやってくる人も少なくない。妻に先立たれた男性で、「ご飯は炊けるので、おかずだけほしい」と来店する人もいる。

こみち食堂の店内
食堂に来られない独居者には弁当の配達もしている。最初は受け取りにも出てきてくれなかった人が、次第に玄関口まで顔を出し、笑顔を見せてくれるようになった。愛育班の活動を通じて目指してきた、住む人の顔が見える昔ながらの地域が洲本に戻りつつある。
「城下町洲本 レトロなまち歩き」は回を重ねるごとに参加者が増え、第5回を迎えた今年も1万人を超える人が訪れた。こみち食堂の近所には、イベントでの出店をきっかけに常設店5店も新たにオープン。週末を中心に営業を行っている。
休日ともなると、ガイドブック片手に“レトロなまちなみ”を散策する観光客の姿が見られるようになった洲本のまち。現在進行中の計画は、週ごとにシェフの替わるレストランのオープンだ。城下町を歩く楽しみが、またひとつ増える。

常設店のチョコレートショップオーナー 雨堤麻美さん

「思いがけず18歳で家業を継ぎ、右も左もわからないまま歩き出せたのは、地域の人たちに支えられてきたことが大きい。『お蔭様で』という気持ちで、お役に立つことがあったらできることをしたい」
そう語る野口さんの好きな言葉は「絆」。
これまでの活動で築き上げた絆を大切にしながら、「住みたいまち」「また来たいまち」と若者が感じてくれるようなまちにするために、自らも絆をつないでいきたいという気持ちのこもった一字だ。

(公開日:H26.5.25)