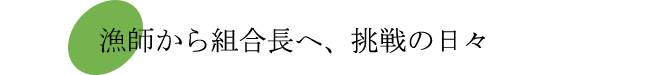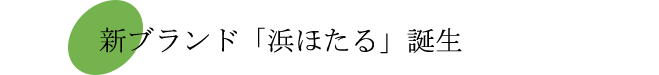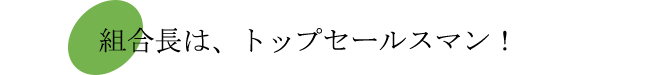漁業を取巻く厳しい状況の中、代表理事組合長として歴代最長4期目を数える川越さん。
「燃油の暴騰で経営が追い込まれた平成24年~25年が一番の危機でした。さらに、消費者の魚離れや魚価の低迷による漁業所得の低さもあります。でも、いちばんの厳しい状況は後継者不足です。子どもたちが家業を継がない。少子化も手伝って、漁師になりたいという若者がいない。組合員の減少に歯止めがかからないのが現状です。」

浜坂港全景
現在、浜坂漁協の組合員は360名(平成28年9月現在)。全盛期の半数だという。そんな現状を前に「浜坂漁港の役に立ちたい」という一心から52歳で船を降り、組合長としてのチャレンジをスタートさせた川越さん。様々な課題がある中で取り組んだのが、日本一の水揚量を誇るホタルイカのブランド化だった。


浜坂港で行われる競りの様子
浜坂漁港で、ホタルイカ漁が本格化したのは30年前。それまでホタルイカは、松葉ガニ漁の網についてくる「ゴミ」でしかなかった。それが今や、漁獲量は年間2,000トンを超え、松葉ガニに次ぐ浜坂漁港の名物となった。

ホタルイカは通常、ゆであげた状態で出荷される。しかし、浜坂漁港では、網からあがったばかりのホタルイカを、船上で生のままパック詰め。獲れたての生鮮状態を保ちながら店頭に並べるオリジナル商品「浜ほたる」の開発に成功。漁の現場とともに8年がかりでこぎつけた。
「漁師たちの理解と協力なしには、生まれなかった製品です。船上でパック詰めをすると、船は操業途中でも製品を降ろしに港へ帰ってこないといけない。漁師の立場からすれば、本当は常に海にいて操業したいんです。そんなリスクを越えて漁師みんなが理解し、快く受けてくれたおかげです」。
漁師と組合が力を合わせて成し遂げた、浜坂漁港・新ブランドの誕生だった。

浜ほたる
こうして生まれたブランドを、どう育ててゆくのか――。川越さんは、情報発信の必要性を痛感している。
「今までの漁業は、魚を獲って市場で売って終わりでした。しかし今は、いろいろ考えながら携わらなくてはならない時代です。必要なものは付加価値と、情報発信だと思っています」。
浜ほたるの販路開拓のため、県の支援のもと平成26年度 農イノベーションひょうごの事業に取組んだ。
「浜ほたるが、大手食品会社の季節メニューに採用されたんです。私自身も流通や飲食など、他業種が集まる場に出て交流するきっかけをいただき、世の中の見方が変わりました」。
浜ほたるの、大手スーパーでの店頭販売もスタート。消費者ニーズがわかるようになり「自分たちのことが、全く知られていなかったことに初めて気づいた」。
それ以来、自らを「トップセールスマン」に仕立てることにした川越さん。「浜坂漁協のファンをつくる!増やす!」ため、温泉でかにソムリエ(浜坂観光協会が設けたカニ専門家)と一緒に企画を提案したり、農林水産省へプレゼンテーションに出かけた。中学校では給食についてのレクチャーに挑み、講演活動も積極的に受けている。これらはすべて情報交換とPRのチャンス!川越さんならではの情報発信だ。


丹波学校給食研究協議会にて講演する川越さん
こうしたトップセールスマンとしての視点を手に、川越さんは新たな目標を見据えている。
まずは、工場をつくって製品化・商品化に力を注ぎ、直販事業のスキルアップと充実化を図ること。さらに、漁業と観光業のコラボレーションを実現することだ。
「遊覧船のお客様にPRがしたいんです。浜坂には、山陰海岸ジオパークや但馬御火浦(たじまみほのうら)をはじめ、海や温泉といった観光スポットがあります。また、カニや魚、但馬牛、米などおいしい食材の宝庫です。でも残念なことに、現在はそれらを活かしきれていません。例えば、船で遊覧を楽しんだお客様が持ち込む特産食材を、その場で料理してお出しする食堂や、加工品をお土産として買ってもらうスポットをつくる。浜坂漁港を、人が集まるホットスポットとして売り出したいと思っています」

浜坂港で現在運航している遊覧船
船を降り、浜坂の海を陸から眺め始めて10年目の秋。販路開拓・消費拡大をめざす経営現場が似合うようになった今でも、川越さんは「できれば漁師に戻りたい」と打ち明ける。
川越さんが船に乗り始めたのは19才の時。22才で船長になった。
「小さい頃から、とにかく海と船が好きで、親と一緒に船に乗って海に出ていました。未知の海を相手に、どうしたら魚が獲れるか考え、工夫し、挑戦する醍醐味を味わいながら、どこまでも魚を追いかけるんです。昔はロマンがありました。のびのびと漁業ができる時代でした」。
時にはロシア領海ギリギリまで出かけ、時には東シナ海をめぐる。北海道の利尻や礼文へも魚を追いかけた。やったらやっただけ、結果がついてくる仕事。
「やりがいのある職業だと思っています」。
だからこそ若者が家業として継げるよう、漁業を守り続けたい。組合長としての頑張りを支えているのは、漁師・川越一男の一途な想いだ。

(公開日:H28.9.25)