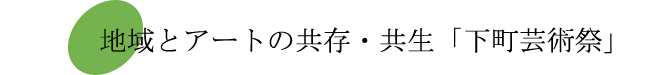*「アートde元気ネットワーク」とは:県内の地域資源と芸術との融合をテーマにしたアートフェスティバルやアートプロジェクトを連携させることで、地域の活性化につなげようという取組み

神戸市長田区で文房具店を営む両親のもと、画材や紙に囲まれて育った岸本吉弘さん。幼い頃から模型づくりや習字、絵や漫画を描くのが好きだったという。
「その分野では、よくほめられていました。」
ピカソやユトリロといった孤高な存在感を放つ画家たちが、カッコよく映った子ども時代。生活も人生も犠牲にし、絵の創造にすべてを優先させた生き方に憧れ、美術系大学への進学を決心したのは高校生の時だった。
画家への夢を胸に東京へ進学。在学中から精力的に創作発表活動を続け、大学の卒業制作、大学院の修了制作ともに優秀賞を受賞。大学での助手や専門学校講師を務めた後、故郷・神戸で教員になる機会が巡って来る。そして2000年、神戸に帰郷。画家・岸本吉弘としての第二章のスタートだった。

岸本さんのアトリエにある画材たち。長い画家人生の中で使い古され手に馴染んでいったもの。
岸本さんが、自身の絵に込めるテーマは「スケール感」。
「色同士、形同士のせめぎ合いを体感してほしい。色やタッチのダイナミズムを直に肌で感じることで、理解できなくても不思議な感覚や疑問が残ったり、その絵をとっかかりに以前と何か違う感覚が生まれたり変わってきたり……。そんな風に、いい意味で人を覚醒させ、根底の生き方さえも絵で変えることができたら。」
そんなメッセージは、教員としてのあり方にも通じている。

個展会場の様子、圧倒するようなスケール感(岸本吉弘個展「絵画レッスン」2016年春)
たとえば、理学部・農学部・医学部といった学生たちへの講義では、多角的に物事を見る機会になればと願っている。
「美術や絵画に触れることは、自分の中にない考え方や感じ方を体験し、豊かな感受性を育む機会です。それは相手の気持ちや立場を理解することにつながり、柔軟な発想力を養うことも可能になります。」
大切なのは「自分には理解できない絵を描いている人もいるんだ」という事実を理解しようとすること。そうした他者理解がその人の生き方につながり、人間形成の本質的なベースになってゆくと岸本さんは語る。
「自分が持っている可能性の引き出しを、絵画表現を通じて開いていく。この経験が私にとって人生の価値になるんです。」
教育や地域に関わるということは、こうした専門性や本質部分を実践レベルに落とし込み、ダイレクトかつやさしく伝えてゆくこと。そんな可能性をたっぷり秘めた贅沢な体験の場のひとつ。それが昨年、開催された「下町芸術祭」だった。

住む人と訪れる人が、非日常の泣き笑いを共有できる「祭り」という体験を、風情漂う下町のくらしと現代アートの融合によってよみがえらせよう――。2015年秋に開催された、神戸市長田区の地域づくりプロジェクト「下町芸術祭」。岸本さんは副実行委員長を務め、担当した絵画プログラムでは11名の画家たちによるグループ展「ウィズ・ぺインター」を開催した。
「長田には、絵を見せるために特権化されたいわゆる美術館といった『箱』がありません。人が見に来る場所がないのなら、こちらから街の中へ出向いていこうと……。本来は展示する場所じゃないところ――レトロモダンな小学校跡や古民家、空き店舗など――や、日常的に暮らす風景や路地を上手に活かすことができれば、今までにないおもしろいものになるのでは? 小さくても豊かなものができるのでは? 今までに無いおもしろさで見せる……挑戦でした。」

下町芸術祭「ウィズ・ペインター」の展示風景(撮影:岩本順平)

下町芸術祭「ウィズ・ペインター」のアーティストトークの様子(撮影:岩本順平)
日常の中にアートがある。生活の中にアートがある。そんな仕掛けが、美術を身近に感じてもらうきっかけになるのではないかと、岸本さんは考えた。
「商店街に作品を設置した時は『そこまでのモノが来るとは思っていなかった』と戸惑わせたり、日常にないものが存在する違和感を与えたことも事実です。夕飯の買物をする隣に大きな絵があるんですから。一方で生活圏内での展示は、日常的な目線や行動範囲の中で目に入ってしまうため、ついつい見てしまう。好奇心とともに、おもしろがってくれる人も多かったですね。」
作品を置くことで「ここに、こんなスペースあった?」と、改めて自分の暮らす地域を意識するきっかけにもなっていった。
「万一トラブルが起こり、打開策を探るために町内会のおじさんのもとへ走らなければならなくても、それが地域をつなぐ役割を果たすことになると思いました。」
懐に一度入れば親近感を持ってくれるのが下町・長田の良さ。「来年もやらないの?」と、いつしか声もかかるようになっていた。コミュニケーションを取りながら、距離を縮める作業を重ねることで地域の将来性が育ってゆく。
「コアな美術をやさしく丁寧に、ときほぐして見せてゆきたい。見る人がわかってもわからなくても、問題意識を持って制作・表現している人間がいることを伝えたい。たとえそこに不協和音が起こっても、制作側は届け続け、運営側は底辺から支え続けること。楽しさだけを優先させるのではなく、表現そのものやその時代の芸術を、見せて知らせることが大切なんだと思います。」
2008年に神戸長田文化賞を受賞した際、作品を展示しても人が集まって来ない現状を目の当たりにした岸本さん。
「当時は阪神・淡路大震災のダメージも大きく、街を離れてゆく人も多かったんです。生まれ育った地域への恩返しとして、アートの力で街を活性化できないか。アートで元気を補いたいという思いは強いです。」
そんな故郷・長田の街に今、少しずつアーティストが住み始めている。中心地にあるダンス系NPO法人にダンス留学にやって来た学生たちが、地元に住みながらレッスンを受けていたり、倉庫や空き店舗をスタジオやアトリエとして利用する芸術家たちも増えているという。

翌年の開催に向け、下町芸術祭実行委員会議が行われた
神戸市内で最も空き家率が高いといわれる長田区(*)だが、アーティストが集まると空き家の再利用が可能になり、街全体の雰囲気も変わる。今は点でしかないコミュニティも、いずれは線、面に拡張してゆくはず。それも、地域に芸術や芸術祭が根付く意義のひとつだと語る岸本さん。
人と人との距離が近く、絡み合わずにはいられない人情味。カッコをつけず作品の意図が「わからない!」と言える正直さ。そんな下町・長田に「アーティストにやさしい街」という新たな顔が生まれることが、これからの街づくりにつながってゆくと話す。
(*)神戸市住生活基本計画統計データ 平成25年住宅・土地統計調査より
「そうした地域の企画も創作活動も、すべて自分の足元から出発するものです。借り物じゃないオリジナリティは、自分の足下を掘ることでしか出て来ない。掘って出て来たものが宝物です。」と話す岸本さん。
「表現も、教育も深いもの。掘り下げてゆくとどこまでも深まり、こんなもんかと留めるとそこで終わる。ゴールや限界は自分で決めるものだと思っていますから、どこまでも先に置きたいんです。それが自分の成長・発展につながるでしょうし、ひいては地域貢献へつながってゆくものだと思っています。」
「こんなもんでいいだろうと思ったら、そこで終わってしまう。」という岸本さん。
自分自身の表現に向き合い、やりきると決めた創作活動。「先生がいちばんエキサイトしている!」と学生たちに言わせるべく、全力で彼らにぶつかる覚悟を固め「自分の理念や創作、現代メディア、現代表現への意見や経験を、逃げずに学生たちに伝えていく」ことに向き合う教員としての日々。
掘り下げ、掘り下げ、掘り下げ続ける先にあるものは、人とアートと長田の街をつなぐ新たなエネルギーに違いない。
クレジット➡取材場所協力:角野邸(運営/NPO法人 芸法)

(公開日:H28.10.25)