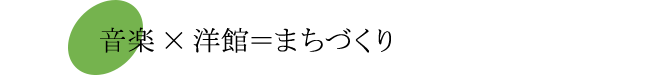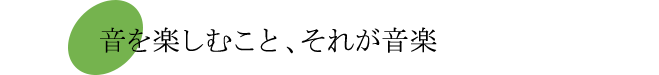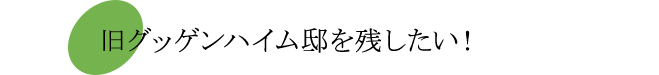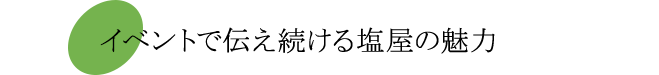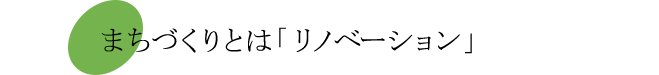海が目の前に広がる塩屋の駅を降りてすぐ、山に向かって複雑に伸びあがる町の中の坂道を歩き、この日の取材先である旧グッゲンハイム邸をめざした。
旧グッゲンハイム邸は、明治45年頃グッゲンハイム家の邸宅として建てられた後、企業の寮として使われていた洋館だ。森本アリさんは、この建物の管理人と音楽家という二つの顔を持つ一方、塩屋のまちづくりにも関わっている。
「“巻き込まれ型”なんです。傍観しておけばいいのに、ついアイデアを出してしまうので、後に引けなくなってしまう」と笑う森本さん。音楽をはじめ、多目的スペースとしての新たな息吹を吹き込まれ始めた洋館は、様々な人が塩屋の町へ向かうきっかけの場所になった。
「まちづくりに興味があったというよりは、強烈な違和感を覚えた出来事があり、その当時はありのままの塩屋を残すべきと、大きな使命感を感じて様々なイベントや制作物を通じて活動しました。その後、洋館の管理運営に携わることになりました。どちらにも共通して言えることは、抱えきれない大きな責任を伴うことも、なるべくなるべく自分が楽しめる方向に持って行くこと。これが持続する秘訣です」という森本さん。塩屋の町に新たな人の流れが生まれた物語のスタートは、森本さんのベルギー留学時代にさかのぼる。

<築100年以上の建物となり、現在は多目的スペースとして活用されている旧グッゲンハイム邸>
進学のため、お父さんの母国であるベルギーに留学した森本さん。
「入学した美術学校が、とても自由な校風だったんです。出された課題に映像で答えてもいいし、絵、小説、彫刻、音楽、どんなもので答えても評価される学校でした。もともと8ミリなどで撮影した音のない映像を映しながら、既存の音楽を流すことをしていたんですが、飽き足らなくなって自分で音楽を創り始めました。」
森本さんの音楽家としての多彩なフィールドの中でも、特にソロとしての活動はユニークだ。演奏に使うのは、ゲームボーイや掃除機といった、およそ楽器とは呼べないものや、口琴(こうきん)という体鳴楽器が中心。
「肩書きは『音楽の敷居を下げ続ける音楽家』です。子どもたちとのワークショップでは、手拍子のリレーで早さを競ったり、ゲーム的に音を楽しむだけで仲良くなれます。楽しむことの基本は、ここにあるんです。」
ユニークな音楽性に磨きをかけ、日本に帰国した森本さん。お母さんのステンドグラス工房を手伝う日々の先に、旧グッゲンハイム邸との出会いが待っていた。

<口に当てて、体を使って共鳴させる不思議な楽器「口琴(こうきん)」を演奏する森本さん>

<楽器ではないものを楽器にすることを得意とする森本さん曰く、音楽は文字通り「音を楽しむ」こと>
「100年を超える歴史の中で、今が一番使われている邸宅です。」
森本さんがそう話すように、結婚パーティーやコンサート、各種教室、ロケ撮影など、貸しスペースとして、日々利用される空間になった現在の旧グッゲンハイム邸。しかし、森本さんが管理人になる以前は、維持管理の大変さから取り壊しの危機に瀕する洋館のひとつになっていた。
「残るという約束で、売買がなされた神戸の洋館が解体され、大きなニュースになりました。それを知った当時の持ち主の方から、建物を残し活用してほしいと、森本家に相談がきました。」

<譲り受けた旧グッゲンハイム邸をプロの力を借りつつ自分たちでも補修>

<毎月様々なイベントが開催され、ローカルな才能から著名な音楽家や海外からのアーティストも出演>
旧グッゲンハイム邸は、昔から当たり前にある塩屋の景色の一部だという森本さん。
「日本の建築の世界は、古さに対する価値観が低すぎる。石の建築と木の建築の違いはあれど、世界には築200年ぐらいの建築はざらにある。それらの建築物は、むしろ価値が上がっていたりします。メンテナンスを怠って、30年の耐久年数でさよならする日本の標準的な家への考え方って、切なすぎる。」
取り壊すことで失われるのは、景色だけではないという森本さん。
「歴史も記憶も、失われる。」
それは帰国後に見た、神戸の町だった。

<今も残る洋館が独特の風景を形成する塩屋の町並み>
森本さんが帰国したのは、阪神・淡路大震災からほぼ一年後のことだった。
「がれきの山は処理され、更地が多くなっていました。日本は復興のスピードが速すぎると感じたんです」という森本さん。
「ヨーロッパでは、今でも町中に過去の痕跡や遺跡が残っていたり、歴史の積み重なりをそのままに見ることができたりします。それに比べ神戸の町は、ただ一掃されているようで、何も考えることなく新しいものにドーンと突き進む感じでした。都市計画でも、長屋があったところに、いきなり十何階建ての大規模な復興住宅ができている。記憶を消すのが早すぎるんじゃないかと違和感を感じていました。画一的で個性のない『のっぺらぼう』な町になっていくって……。」
比較的ダメージの少なかった塩屋は、区画整理も行われず、昔のままの姿が残り幸いだったと森本さんは感じていた。しかし一方では、被害の大きかった町は新しく開発され変化していくのに、塩屋だけが何も変わらず取り残されていると感じた人たちも多かったという。

<六甲山脈の西端、海と山に挟まれた小さな町、塩屋>
「塩屋の町並みがそのまま残ったことは、恵まれていることなんだとわかってもらいたくて、町を多角的に楽しむイベントを始めました。」
そのひとつが平成26年から続く、塩屋の町を舞台にした文化祭「しおさい」だ。商店街の空き店舗を利用したアート作品の展示やワークショップ、ビルの屋上や人の家の庭、バルコニーなど、塩屋ゆかりの音楽家たちが30組以上も町の中で音楽を奏でる「しおや歩き回り音楽会」などを開催。小さな塩屋の町に、300人もの人が訪れるイベントになった。「中からの視点も外からの視点も大切。塩屋の場合、町並みが変わらないことが、いつの間にか、町の希少価値を高めていた。町の人も、そのことに気づき始めた」と森本さんが話す通り、商店街には、カレー屋、カフェ、ピザ屋、レコード店などの、若い商店主が構える店が増えた。どこか人なつっこい雰囲気、そして車の入ってこない歩き回りの町を気に入り、子育て世代や若い世代も増えている。そんな塩屋のまちづくりを、森本さんは「リノベーション」と表現する。

<コンサート・展示・ワークショップなど、平成26年から継続している塩屋の文化祭「しおさい」>
塩屋のまちづくりに必要なのは、町のスケール、つまり「規模」を変えないことだと話す森本さん。
「時と共に中身は変わっていくし、外観が変化するのもしょうがない。でも、1戸の邸宅がマンションになるとスケールが変わります。元々のサイズ感を守りたいんです。世の中、新しいものを生み出すことが最も価値がある時代はとうに終わってるんじゃないかな。中身を少しずつ改良していき、家も再活用・利活用を積極的に考えないと。塩屋の中古住宅のリノベーションは面白いものが多いですよ。」
例えば古びた駅前商店街を取り壊し、ロータリーをつくることが、まちづくりではないという森本さん。
「塩屋は、町の中そのものがリノベーションで息長く残っている感覚です。勝手気ままで人間くさい、雑多な感じが魅力。スーパーではなく、会話を楽しみながら小売店で買い物を楽しむ、そんな生活が楽しめる町。これが、本来あるべき町の大きさじゃないか。そういうところが、この町の価値だと思うんです。」
そう言って森本さんは、塩屋の町の大きさを「人間サイズ」と呼んだ。

<「駅前でみんな通らざるを得ないから、塩屋ではお互い見知った顔が多い」と森本さんが語る塩屋駅前の塩屋商店街(写真:片岡杏子)>
塩屋の町の中には、実は信号が一つもない。
「最近は、それが自慢になったりします。『普通電車しか止まらないのも悪くないよね』って言われたら、『ATMがないのも、さらにいいぞって(笑)』。便利になりすぎたことで、かえって”ちょっと不便なこと”が楽しめる?というふうに、町の評価が変わってきたと思うんです。最初から車を持たないという選択をして、車が少なく人が道の真ん中を歩ける町がいいと、子育て世代が塩屋に住み始めるケースも増えています。」
歩道を確保する道幅もないため、すれ違いざまに「すみません」と言葉をかけ合い、コミュニケーションをとらざるを得ないところも魅力の一つ。

<森本さんが大事にする、震災前からの風景を色濃く残した、ノスタルジックな塩屋の町並み>
「車が通れないのは当たり前くらいの『ちょっとややこしい』この細い路地も『人間サイズ』。塩屋のいいところです」と森本さん。
「新しくできた店の3歳児が店の周りをうろうろして、その子を隣近所の店主たちが共同で見守るようになると、そこに新たなコミュニケーションが生まれ、子育て中のお母さんたちが集まるようになったり。一つの家族や一つの店で、町が変わるんです。この町のスケールならではの、コミュニティのでき方でしょう?」と微笑んだ。
「家々が肩を寄せ合っているみたい」。
家の屋根が、いろいろな方向を向いて建つ塩屋の町。その様子を表現したこの言葉に、森本さんは魅了された。肩を寄せ合う家々は塩屋の原風景、まさに人間サイズの町そのものだ。

(公開日:H30.02.25)