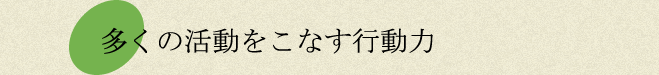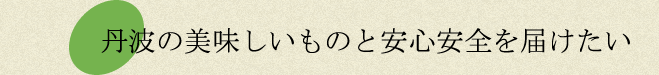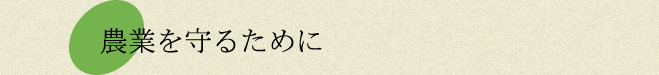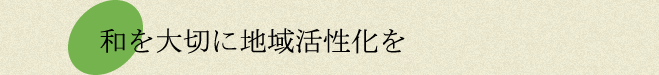丹波市。農業が盛んなこのまちで、生産者が大切に育てた農作物を、一人でも多くの人に届けようと活動を進める人がいる。
企業組合氷上つたの会理事長秋山佐登子さんにお話を伺った。

丹波市氷上町にある丹波市立地方卸売市場。その一角に一棟の調理施設がある。
「企業組合氷上つたの会」の食品加工所だ。調理場に入ると、大納言小豆を使ったご飯が炊き上がったところ。辺りが小豆のいい香りに包まれる。
つたの会では、地元丹波産の四季折々の食材を使った商品を開発。郷土の味、おふくろの味を届けたいと、添加物を使用せず、手作りにこだわって製造加工している。商品は地域の野菜直売所や道の駅、県内で催される各種イベントなどで販売。ネット通販や百貨店で購入できる商品もある。
秋は栗、少し経つと枝豆に変わり、冬は里芋…と移り変わる丹波の四季を楽しむことができる。「丹波はいつの季節もおいしいものがあるのよ」と秋山さんはほがらかに笑う。

「つたの会に頼んだら間違いないと思ってもらえるように、がんばっている」そう語る秋山さん。今から3年前の平成22年に、2代目理事長に就任した。
平成5年、地場食材を利用した加工品づくりをきっかけに始まったつたの会の活動。
初代理事長の大木智津子さんは、地産材料を使った安心安全な食品づくりと農村女性の就業機会創出をめざして、つたの会を設立。自ら家業の酪農業を取り仕切りながらも、加工場の建設、調理用設備の整備など、必要とあれば役場との交渉や資金集めに奔走し、つたの会の礎を築いた。
やがてつたの会は、平成21年には兵庫県農業賞や「第19回食アメニティコンテスト」農林水産大臣賞を受賞するほどの組織となる。
それに前後し、経営から退くことを決めていた大木さん。後継者として白羽の矢が立ったのが、産直センターやいずみ会など、地域で精力的に活動していた秋山さんだった。
実は秋山さん、つたの会には、誘われる形で入ったにすぎなかった。
「始めはお味噌作りを手伝うために入ったはずが、あれよあれよという間にそうなっていって」と笑う。
各製品の製造部門を経験し、イベントで遠出する道中には、大木さんからつたの会の理念を教え込まれた。気がつくと役場の人や取引先に「私の後継者です」と紹介されるようになり、本当に大木さんの功績を引き継ぐことになった。

秋山さんの1日は、午前2時半、家業である新聞と牛乳の配達から始まる。
7時過ぎにはつたの会へ。理事長といっても他のスタッフと何ら変わりはなく、担当する商品づくりに勤しむ。

てきぱきと小豆のご飯を詰める秋山さん
完成した商品の配達にも回る秋山さん。この日は丹波市栗振興組合からの依頼で、栗の品評会での昼食用に、丹波産の栗をふんだんに使った栗ごはん弁当を配達。加工所と会場を何度も往復し、現地ではスタッフと一緒にお弁当を配る。

特製の「栗と小豆のご飯」。栗生産者のみなさんも納得の味。
配達が終わる時間には、みんな揃って一休み。食べているおやつの味や原材料から新しい商品のアイデアが生まれることもある。

休憩中のワンシーン。たわいのない世間話が、商品の改良検討会になることも。
休憩がすめば次の日の準備と、長期保存ができる商品の製造が始まる。
そういった諸々の業務の途中にも、事務所で経理担当者とのやりとり、材料の買い出し、イベントの調整など休みなく働く。携帯への着信もひっきりなし。
秋山さんと20年来の付き合いのある農産物生産者は、秋山さんの人柄を「元気はつらつ。てきぱきと物怖じせず働く人。私生活をつぶして人の3倍は働いてるんじゃないか」と語る。
新商品の開発には秋山さんのひらめきが生きる。
生産者や産地の人間が美味しく食べているのに知られていない、そんなものを、多くの人に届けられる方法を思案することが、商品開発の肝だという。
例えば試作中の「丹波の宝石箱」。秋の栗、枝豆以外もふんだんにある丹波産の野菜や果物を紹介したいと企画した。
丹波産の食材ひとつひとつを小さなゼリーにして、宝石箱のように丹波の1年を詰め合わせて楽しむのが、この商品のコンセプト。風味と形を残すのに苦心したというが、ブルーベリーや桃、マクワウリ、生姜、ミニトマトなど11種類が商品化される予定だという。
また、味や安全性に全く問題がないのに、色形だけを理由に商品価値が下がってしまった農産品に光を当てることもある。
イベントなどで販売される熱々の「玄米団子」がその一例。

兵庫県民農林漁業祭で販売されたつたの会の玄米団子。ぷちぷちと玄米の食感が残る。
玄米団子のレシピを教えてもらった時、米の等級付けを担当する農産物検査員の経験から、秋山さんはひらめいた。
国の基準では整粒(きちんと整った形の粒)の割合で、三等米とつくものがある。そうなると味は変わらないのに買い手がつかないか、買い叩かれてしまう。
「つぶして使うお団子なら、生産者が同じように丹精込めて育てたお米を活かせるじゃないか!と思いついたんです。生産者は信頼の置ける方ばかり。だから、等級だけに頼らなくても安全性も判断できる。一等米でも三等米でも味が良く納得できるものを材料にしよう、こんな考えからつたの会の玄米団子は誕生しました」
そんな秋山さんのことを、丹波市観光協会の足立さんは、「研究心が旺盛。売り込み方が上手な、食の達人」と解説する。
都市部でのイベント販売でも、添加物は使わないというこだわりもあって、特に子育て中の父親母親からの評判が高いという。
旧春日町の兼業農家の家に生まれ育った秋山さん。大学進学や就職で都市部へ出る同級生は多かったが、「入試で必要な英語がどうにも苦手で」と地元に残り、家業を継ぐことに。丹波市農業委員会、JA丹波ひかみ女性会、丹波市食育推進会議委員会、兵庫丹波生活研究グループ連絡協議会など、若い頃から農業と食に関わることに数多く携わってきた。
そんな秋山さんの活動のルーツは、立ち上げから運営に関わった「丹波氷上産直センター」。

丹波氷上産直センター。生産者が販売用の枝豆を預けにやってくる。
20年程前、農産物の販売方法と言えば農協販売が中心だった。規格外のものや無農薬野菜などは販路がなく、無料で近所に配るだけになっている生産者も多くいた。
手をかけて育てた作物が、売上として形になればやりがいにもなるはず。たとえ小さな仕事であっても、自分の働きが報われるような、そうした形を大切にしたいと、宅配やアンテナショップを通じて、生産者か消費者に直接販売できる「産直センター」の立ち上げに参画した。
「生産者のやりがいを守るのは丹波の農業を守ることにもつながる。それと、丹波のおいしいものを広く伝えることは、都会に出ず地元に残ったものの責任だとも思っている」と話す。

産直センターの活動には夫の正光さんとともに関わる。公私共に支えあう二人だ。
そしてつたの会。70歳代の女性たちも多く活躍している。専業で農業や酪農に従事してきた人、定年退職を機会に声をかけられた人など、様々な経歴を持った人たちが、製造、事務、経理、広報とそれぞれに力を発揮している。
わいわい賑やかに作業できるこの場が楽しいと話す秋山さん。役職が務まるような器じゃない、本当は裏方で動くのが性に合うのだと言いながらも、メンバーたちの働く場を守るために腐心する。夏に売れない餅を季節限定にするなど、時には業務の整理も行った。「みんな誇りを持って作業にあたっている分、そうしたことをお願いするのは本当に心苦しかったけど、理解をしてもらった。」
理事長就任後、売上は一度落ち込んだものの、経営のスリム化もあり、平成24年度は収益を伸ばすことができた。時給も毎年少しずつではあるが増額している。

神戸市内の商店街での販売風景。つたの会で開発された加工品と産直品が並ぶ。
今では、有名百貨店のおせち料理のカタログにも、つたの会の名前が並ぶ。
「作る人達がいいものをしっかり作ってくれる。もっと多くの人に丹波のおいしさを伝えられる新しい商品をどんどん開発していきたい」とこれからの展望を語った。
農業が中心のこのまちでは、農作物の生産者が元気になると、地域が元気になる、と秋山さんは考える。おいしかったよ、の声が食べた人から直接届くことが、作り手の活力になる。少しの工夫によって、地域の外ともそうしたつながりをつくる、そんな活動を秋山さんは続けている。
秋山さんにとって地域活性化とは?との質問には、大きなことは考えていないけど、と前置きし「身近な人たちを『いい感じ』にすると、地域振興につながるんじゃないかな」との答えが返ってきた。
秋山さんが大切にしている言葉は「和」
家族や支えあう仲間、作り手たちと「和」となり、この地域を盛り上げていく。

(公開日:H25.10.25)