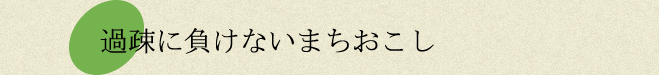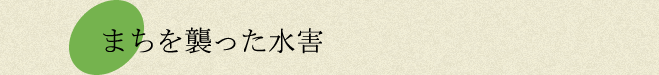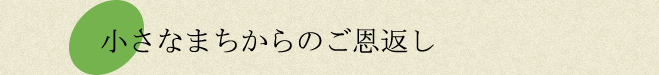生まれ育ったわがまちの商店街を盛り上げようと日々まちづくりに奮闘しながら、豪雨水害で被災した商店主として、そのときに受けた支援の恩返しをしたいと、東日本大震災の復興支援に取り組む人がいる。
空き缶でもうけてもええ会事務局長千種和英さんにお話を伺った。

岡山県との県境、中山間地域に位置する佐用町。その町の中心部、JR姫新線佐用駅前に約40軒の商店が連なる佐用商店街がある。
千種さんはこの佐用商店街に生まれ育った。家業はLPガスの販売業。子どもの頃はよく軽トラの助手席に乗って、ガスボンベの配達について回った。そこで出会った色んなお客さんと心やすく話をする父親を見て、小さいながらに自分も跡を継ぐのだと心に決めていた。
「ガスという生活必需品を扱っていたこともあって、お客さんの家に勝手に入って作業することもあった。逆にそうしないとお叱りを受けるような関係でもあったんです」
小さなまちの住民と商店の信頼関係。こうした人間同士のしっかりとしたつながりが、千種さんは子どものころから大好きだったのだという。
願いどおり、24歳の時に、父のもとで仕事を始めた千種さん。商工会の青年部にも入り、先輩たちに可愛がられながら毎日仕事に、商工会活動にと励んでいた。
ただ、若者の流出や大型店の台頭で、次第に元気をなくしていく商店街に、先の不安を感じ始める。
30歳を過ぎた頃、千種さんは佐用町が立ち上げた商店街を中心としたまちの活性化検討グループのリーダーとなる。集められたのは同世代の住民や商店街関係者。買い物客を増やし、佐用商店街を活気づける策を編み出そうと、全国の商店街の先行事例を持ち寄って学んだ。それぞれに魅力ある活動。商売を成り立たせて、地域を元気づけるような取り組みが全国各地で進められていた。
被災からの復興、学生を巻き込んだ取り組み、過疎高齢化にどのように立ち向かうか――それぞれに抱える課題は異なるが、その理念や手法に学ぶものは多かった。
そして千種さんは事例集を読むだけでは飽きたらず、自腹を切って全国の商店街に足を運んだ。
そこで感じたのは、商店街活性化は集客だけで終わるという代物ではないということ。魅力的な地域にこそ、人が集まり買い物客が増える。個性のある魅力的なまちをつくろうと奔走する商店主や住民の熱を、千種さんは肌で感じたのだという。
「要はみんな筋金入りの『まちづくりバカ』なんですよね」
志を同じくする全国各地の仲間との縁が、ここから始まった。

全国から商店街の有志が集まる全国リサイクル商店街サミット。(宮城県南三陸(旧志津川)町・平成17年)
特に感銘を受けたのが東京の早稲田商店街の空き缶回収の取り組み。回収機に空き缶を入れると商店街で使える金券や割引券、それに商品が当たる仕組み。楽しみながらリサイクルと集客を兼ねる当時画期的なシステムだった。
ぜひ佐用でもやりたいと、千種さんが立ち上げた団体が「空き缶でもうけてもええ会」。
早稲田商店街へ何度も足を運び、そのユニークな手法を学び、佐用でもその空き缶回収機の導入を実現させ、まちの大きな話題となった。
その後も千種さんは各地の取り組みにアンテナを張り、これはと思う取り組みはどんどん吸収していった。
例えば住民自らが、佐用の地域情報を伝えるテレビ番組「佐用チャンネル」。
熊本県で始まった「住民ディレクター」の活動を佐用でも始めた格好だ。
制作に参加する住民が増えるまでは、企画、レポーターや編集などの作業を千種さんが担当。一時は「商店街の千種さん」より「TVレポーターの千種さん」として、声を掛けられるほどだった。
そして佐用の名を一躍有名にしたホルモン焼きうどんの取り組みにおいても、千種さんは中心的な仕掛け人のひとりだ。
神戸長田のそばめしに注目が集まっていたこともあり、新長田の商店街との対決イベントを仕掛けた。ご当地グルメブームに乗り、新長田のそばめしや高砂のにくてんなど県内のご当地グルメとともにそれぞれの地域の盛り上げに成功した。
ただ千種さんが細心の注意を払ったのは、ブームに過剰反応しないこと。
小さなまちで、大きなブームに合わせた商売を始めたら、そのブームが過ぎ去った後に負債だけが残ってしまう。何に取り組むか、その内容も大切だが、まちづくりのために取り組むことを見失ってはいけない。
まちの体力を損なわないように、それでいて歴史や魅力を最大限に引き出すような商品やイベントでまちを盛り上げたい。ふるさと佐用を愛するがこそ、そこにある資源が花開くようにじっくりと腰を据えて、千種さんはまちづくりに取り組んできた。
平成21年8月。突然、佐用町が大きな水害に見舞われる。兵庫県西・北部豪雨水害だ。
記録的な大雨で佐用川が氾濫。まちの中心部へ水が流れ込み、広範囲に渡る浸水を引き起こした。死亡者18名、行方不明者が2名、全壊半壊あわせて891棟に及ぶ甚大な被害をもたらすことになる。

水害の当日、千種さんは神戸市新長田の商店街にいた。第一報は消防団からの出動要請。妻と連絡がつき、家に水が入ってきたと知る。車を飛ばして佐用へと戻った。近くの高台までたどりついたものの、水が引くまでは危険だと止められる。妻や子どもたち、両親が待つまちへと入ることは許されなかった。
夜中になり、やっとまちに入ることができた千種さんが目にした光景。
街灯も消え、真っ暗なまち。どこかから流れ着いたたくさんの車がひっくり返り、ショートして火花が散っているものもある。水が入りこんで故障しているのか、延々とクラクションが鳴り響く。
「辺り一面臭いもひどく、とてもこの世のものとは思えないような異様な光景だった」
とにかく第一に考えたことはガス漏れが起きていないか。自分のお客さんであろうがなかろうが、同業者同士声を掛け合いながら暗闇の中を歩いて回った。
やがて白々と明けていく空。明るくなってみれば、店舗を兼ねた我が家は一面の泥に覆われ、大規模半壊。外に出てみれば街全体が壊滅状態となっている様子が改めてはっきりと見て取れた。
「2~3日の間、泥かきを続けたけど一向に先が見えない。何もかもが泥にまみれ、水に浸かったところすべてに泥が入り込んでいた」作業はいつ終わるのか、暗澹たる気持ちになったという。
そんな千種さんを救ったのが、全国各地の仲間たちからの励ましの声だった。
佐用を盛り上げたいと活動を続けてきた10年の間に千種さんが出会ってきた多くの人たち。場所は違えど、まちへの愛を熱く語り合い、それぞれの現状の厳しさに一緒に頭を悩ませ、必要ならば知恵を出し体を動かし、汗をかき手伝いあってきた仲間たちだ。
「お前しかできないことがある。お前の役割を果たせ」叱咤激励の声に、千種さんは自分を奮い立たせる。千種さんは家の復旧作業は家族や知人に任せ、地域のために動くことを決めた。
続々と到着するボランティア、物資や義捐金。それぞれがうまく配分されるよう、町外からの問い合わせで鳴り止まない電話を手に、地域のコーディネイター役として奔走した。

各地で頻発する自然災害を受け、いま全国で、災害被害を最小限に抑えることができるよう、発災後の対応までを見通した防災・減災の取り組みが進められている。
佐用の経験は、まちの大小に関わらず、全ての地域が取り組む災害に強いまちづくりに活用してもらえるはずだ。千種さんは、被災地佐用から、全国から受けた支援に対するお礼のひとつとして、復旧が進む佐用に見学者を受け入れるとともに、呼ばれれば遠方でも講演に出向き、被災経験や教訓を伝えている。
「佐用では全国から多数のボランティアが駆け付けているのに、どこに頼めばボランティアが来てくれるのか知らない人、遠慮があって本当にしてほしいことをお願いできない人がたくさんいた」
ボランティアセンターは何をする所で何をお願いできるのか。ボランティアで来てくれる人にはどんな応対すればいいのか。いずれは帰ってしまう人たちに今頼るべきなのはどんなことか。
ポイントは、ボランティアの受け入れシステムを整えることだけでなく、こうした住民一人ひとりの受け入れの心構えや知恵といった部分も合わせた、いわば地域の『受援力』と呼べるような力。
せっかくの支援を最大限に活かすため、この受援力を日頃から高めておく必要性を伝えたいと千種さんは語る。

ボランティアに対する住民からの感謝のメッセージ
例えば、小学生に対する災害学習。
一緒にまちを歩いてまわりながら、まちの至るところに貼られた水害時の水位を表したステッカーや、立ち止まって大きく引き伸ばした写真を見せながら、どのような被害を受けたか、ひとつひとつ説明する。
「災害時に必要となるのは人・お金・もの・情報・スピード―」
全国から多数の支援ボランティアが駆け付けてくれたこと、復旧にはお金がかかること、どんな時でも確かな情報に基いて冷静になること。何が、何のために必要になるのか、子どもたちにもわかるように丁寧に解説する。
「元気なまちになることと、語りつなげることの2つが佐用の支援へのご恩返しだと思っています。ぜひみんなも帰って家族や近所のひとにお話ししてください」千種さんは子ども達にいつも呼びかけている。

たつの市立新宮小学校の総合学習での一幕。佐用の被害状況を説明する千種さん。
町外の小学生も積極的に受け入れている。
そして、佐用の水害から1年半後、東日本大震災が発生する。
真っ先に思い浮かんだのは、あの水害のとき、一番に連絡をくれた宮城県南三陸町の商店街のメンバーのこと。
ただ、今自分たちに何ができるかわからない。すぐにでも向かいたい気持ちを抑え、状況がわかるまでじっとがまんした。やっと直接連絡がとれたのは発災から1週間後。
「第一声は『生きてるよ―』だった。現地でみんながんばっていることは伝え聞いていたから、佐用にできることがあったらさせてほしい、今は何もできないがいつでも支援する準備だけはしていることはわかって欲しい。そう伝えました」
3月末には、千種さんは県のボランティア先遣隊として、佐用や県内各地のネットワークを駆使して仲間たちとともに宮城県内での炊き出しに駆け付ける。南三陸に直接入れなくても、できることで東北を応援したい一心だった。
4月、南三陸の商店街のメンバーからまた一本の電話があった。
「商売を再開するよ!でも何もないからテントや売るもの持ってきて!」電話口から聞こえてきたのは、力強い一言。地域を元気づけるため、彼らが福を興すという意味で『福興市』を開催するという知らせだった。
「売るものないのに、商売をするよっていうのがなんともうれしい話で。商売人がまちを元気にするひとつの方法だなぁって思った」と振り返る千種さん。
現地は店舗となる施設も設備もないような状況。千種さんは3張のイベント用テントを佐用や近隣の仲間の協力により調達し、南三陸町へ駆けつけた。

福興市で行われた炊き出し。普段のネットワークを駆使して、温かい食事とイベント用テントを届けた
6月からは全国商店街支援センターの依頼を受け、東日本大震災商業復興支援マネージャーとして、岩手県宮古市の商店街支援も始めた。そこで同じく被災した商店主という立場からひとつ伝えていることがある。
「もし跡継ぎもおらず、借金もなく、他に何か仕事のあてがあるなら。店をたたむこともひとつの選択肢ですよ」
被災者にとっていつもの商いが続けられることは、それだけで力になる。店主にしたって元に戻れるならそれ以上に嬉しいことはない。
「しかし、被災以前からの借金を返すため、さらに再建のために費用を使って、辞めるに辞められない商店主の辛さ、厳しさもあるんです」
廃業することが不幸なことのように語られるが、実はそうとも限らない。時には、被災した商店主からはどやされる時もある。しかし、佐用でも辛い例を見てきたからこそ正面から伝えていくのだと千種さんは語った。
千種さんが実感をこめて語る、商店主にとっての復興の難しさ。これは、阪神・淡路大震災の被災地、神戸市の新長田で千種さんが教えられたことでもある。
新長田の商店街メンバーとは十数年来の関係で、特に、まちの復興をリードする大正筋商店街の伊東正和さんとは、仲間でありながら師弟関係のような間柄でもある。
商店の復興について語る時、いつも思い出すのは伊東さんからの一言。
阪神淡路大震災から5年を過ぎた頃、新長田を訪れた千種さんは、きれいに立ち並ぶ再開発ビルを見上げ「いいなぁ、災害に遭ったらきれいにしてもらえていいなぁ」と一言漏らす。
冗談ともつかない千種さんのその言葉に伊東さんが釘をさした。「建物がきれいになることになんの意味もないで」
震災で壊滅的な被害を受けた新長田の商店街は、テント、仮設店舗、再開発ビルと移転を繰り返した。商店街は新しく大きくなったが、昔の住民は減り、買い物客は戻らない。きれいな街並みに合う服装がないと、買い物に出ることがおっくうになったというおばあさんまでいる。
災害だけでなく、再開発が一人ひとりの暮らしを変えてしまった。
その変化は、地域の暮らしと住民との信頼関係の上に成り立っていた個人商店に追い打ちを掛けた。
見かけのきれいさは『復興』とは違う。まだ被災経験がなかったころの千種さんの胸に、伊東さんの一言は深く刻み込まれた。

佐用と新長田。お互いの斬新な取り組みに刺激を受け、切磋琢磨できる、良きライバルだと笑う
そして今、千種さんは佐用で、『復興』の意味を考えている。
ひとつひとつの家や店舗の泥をかき出すことから始まった佐用の復旧作業。
ライフラインが戻り、建物が修理され、今は氾濫を防ぐための河川工事が進められている。しかし、これは復旧であって復興ではない。
復興とは、まちが元に戻るとは、どういうことか。
佐用ならば、過疎のまちに戻すということでは決してないはずだ。
今はまだどのようにすればいいのかはっきりと答えは出せていない。ただ次の世代が暮らしていけるまちにすること。それだけはやりとげたいと千種さんは固く誓う。
千種さんが大切にしているのは『縁(えにし)』。
縁によって出会った人から受けた教えと助けで、今の自分がある。だからこそ、その恩を返していきたいのだという。
「ただ、ご恩返ししているつもりが、いつもまたそこから学ぶこと得ることばかり」と千種さんは笑う。
一人ひとりの経験や思いをつなぐ。愛するわがまちを支える力は、縁によってより強くなる。

(公開日:H26.1.25)