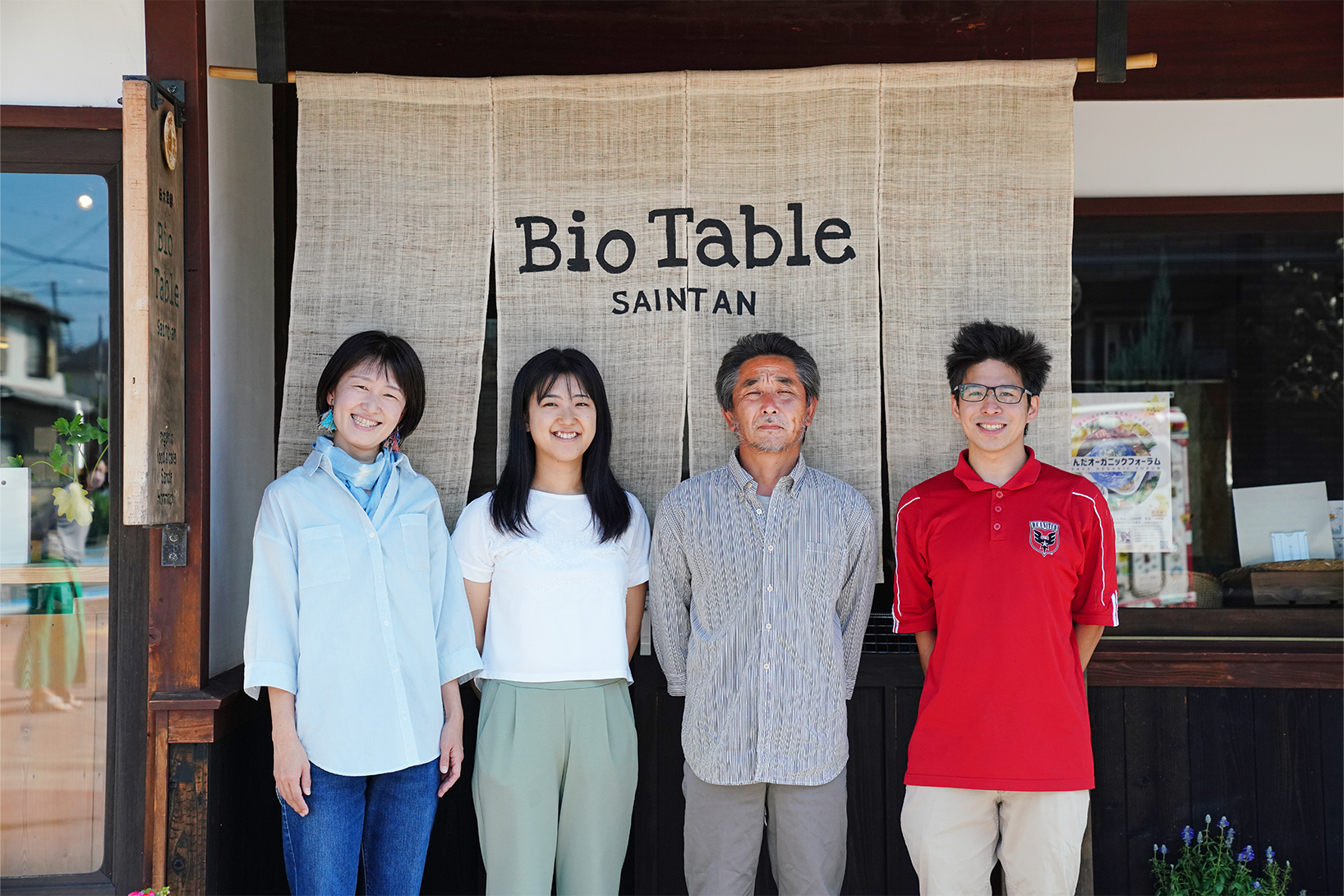目次
多世代がゆるやかに集う場づくりで
地域の子育て力を高めたい!

多世代がゆるやかに集う場づくりで
地域の子育て力を高めたい!
閑静な住宅街の一角で、のぼり旗が風に揺れている。子どもたちが大好きな、駄菓子屋の開店を知らせる合図だ。学校でも家庭でもない第3の居場所として、子育て中の母親たちが地域の中に立ち上げた「みんなのお茶の間 ゆるり家」。子育てを「孤育て」と表現することもあるほど、現在の母親たちの多くは、孤独感や孤立感を抱えながら育児に励む。そんな母親たちと不安や悩みを分かち合い、集まってくる子どもたちに寄り添っているのが「ゆるり家」だ。目指しているのは、多世代にゆるやかなつながりを育み、地域で見守り合い、支え合う関係をつくること。14 年間の長きにわたり、ボランティアとして活動を続けている。
【みんなのお茶の間 ゆるり家(や)】
平成21年、加古郡稲美町で子育てサークルを主宰していた濱田理恵さんが、サークル仲間だった佐々木佳子さん、田口結子さんと共に、地域の大人や子どもがゆるやかに集う場を目指して立ち上げ。おしゃべりをしながら子どもを見守る子育てひろば、児童館のような駄菓子屋、中高生のための自習室の提供といった定期的な活動に加え、子どもたちによるまちづくりイベントの開催などを通じ、子どもや子育て中の母親と、社会をつなぐ活動に取り組んでいる。
おしゃべりで、孤独な子育てから抜け出そう
「縁があったんだと思います。」
3人に「ゆるり家」の開設を決心させたのは、築50 年を過ぎた一軒の家との出会い。開設以降、大人も子どもも、ゆるやかに集える場づくりの活動拠点として「ゆるり家」を守り続けてきた。始まりは平成12年、濱田さんを中心に、子育てサークルが生まれたことだった。静岡県出身の濱田さんは、結婚を機に稲美町に移住。初めての土地で頼る人もなく、孤独な子育てに追われていた。
「子育て支援センターでの活動は、子どもを遊ばせるためのものでした。せっかく参加しても、そういう場になじめず、ぐずる我が子をあやすうちに集いは終わってしまう。とにかく、誰かとおしゃべりがしたかったんです。」と濱田さんは振り返る。
当時、濱田さんの心の支えだったのが、2人の子どもを出産した助産院で開かれる、母親の会だった。子育ての悩みをしゃべったり、育児経験者たちが話を聞いてくれたりする中で、少しずつ友達が増え、「稲美町でも、おしゃべりの会を始めよう。」と、子育てサークル「はらっぱ」をスタートさせた。
あっという間に増えた20人の仲間と共に、子育ての想いを語り合う「しゃべろっ会」や、外遊びを楽しむ「あそぼっ会」など、様々な活動に取り組むうちに、濱田さんたちは子育て支援を仕事にできないかと、考えるようになった。
「仕事に復帰するお母さんなど、子どもの成長とともに仲間の状況が変わっていくにつれ、サークルの運営をボランティアで続けることが難しくなっていきました。ちょうどそんな頃、初めて学童保育に待機児童が出たことで、学童保育のような子育て支援サービスに、ニーズがあるのではないかと考えたんです。」
しかし、祖父母に援助を頼めるため、民間サポートを必要としない家庭が多いことに気づき、早々に断念した濱田さんたち。その一方で、どうしても諦められないものがあった。
「最初に、場所を探し始めていた私たちに、不動産屋さんが紹介してくれたこの家です。せっかく『子どもが出入りしてもいい』と言ってくださったのに、お断りするなんてできませんでした。」
濱田さんは、自宅で開いていた学習塾の教室を「ゆるり家」に移し、佐々木さん、田口さんも、それぞれ仕事を続けることで、家賃などの維持費を自分たちで負担しようと決心。この家を拠点に「ゆるり家」の活動を始めることになった。

子どもから大人まで、みんなが集える居場所
「ゆるり家」の主な活動の一つが、子育てひろば「よっといday」。いろいろな世代の人が集まって、ゆるくつながれる場を目指し、月1回開いている。
「お母さんたちは子どもたちを遊ばせ、お茶を飲みながらおしゃべりをし、ゆったり過ごすことができます。『子育てひろば』というと、未就園児が対象だと思われがちですが、子育てはずっと先まで続くもの。小学生、中学生、高校生、もっと大きくなっても、親は悩んだり迷ったり、誰かに相談したくなったり、愚痴を言いたくなったりします。若いお母さんたちは、先輩ママとのおしゃべりで肩の力が抜けたり、先輩ママたちは昔の自分や子どもを思い出し、小さい子たちに癒されて、温かい気持ちになれます。」と濱田さんは話す。
一方、児童館のような役割を果たすのが、駄菓子屋「おきらくだがしかし…」。毎週水曜日の放課後、地域の子どもたちに「ゆるり家」を開放。子ども同士の口コミを通じて、多い日は約60人が訪れることもある。駄菓子を買って公園に出かけていったり、買った駄菓子を食べながら「ゆるり家」で遊んだり、宿題をしたり、子どもたちは好きなように時間を過ごす。時には、地域の特別支援学校の子どもたちが、買い物体験に訪れたこともある。
「並べているのは30円までのお菓子だけ。買い過ぎる子どもには『大丈夫?』と、声を掛けながら見守ります。たまに、子どもの“人生相談”の聞き役になることもあるんですよ。先日は、高校3年生の2人が、『前を通ったら懐かしくなった』と言って、駄菓子を買いに寄ってくれました。やんちゃな小学生だったのに……。」と、佐々木さんは目を細める。
駄菓子屋を楽しんだ子どもたちが帰った後は、中高生たちの時間だ。コロナ禍をきっかけに、令和3年から始めた放課後自習室「まなぼぅや」。稲美町内に中高生の自習場所がないことを残念に思い、学習支援活動の場として、また地域の居場所として、毎週水曜日の夜に開いている。生徒たちは、学校の課題に取り組んだり、わからないところを教え合ったり、一人で黙々と受験勉強をしたり、使い方はそれぞれ。時々、地域の方が差し入れてくれた手づくりの夜食を、ふるまう日もあるという。
その他、トライやる・ウィークの受入れ事業所としての活動や、稲美町の子育て支援拠点「いなみっこ広場」で開くおしゃべり会「しゃべろーや」、大人も子どももボードゲームで楽しめる「ドイツゲームであそぼぅや」など、様々な活動を続けてきた。
そんな中、「ゆるり家」が10周年の節目を迎えた令和元年から、取り組み始めたイベントが「こどものまち」だ。


子どもが取り組むまちづくり「こどものまち」
「こどものまち」とは、仮想の「まち」を子どもたちだけで運営していくイベント。昭和54 年の国際児童年にドイツのミュンヘン市で行われた「ミニ・ミュンヘン」が発祥とされ、子どもたちが、自分たちの手で「まち」を運営し、働き、遊びながら疑似社会を体験。社会の仕組みや、社会参画を学ぶことができるプログラムだ。
「まち」に出店する様々な店は、事前に募集した「こども店長」たちが、イベントの開催に向けて「こども会議」を重ね、「こんな店があったらおもしろい」と、イメージを膨らませながら、自分たちの手で作り上げていく。参加する子どもたちは「まちの住民」として仕事をし、用意された「こどものまち」独自の通貨で給料を受け取って税金を納め、買い物やゲームを楽しみながら「まちづくり」を体験する。
高砂市や加古川市、播磨町では、NPO法人によって10年以上前から開催されており、かつては稲美町でも開かれたことのあるこのイベントを、自分たちで手掛けたいと思っていた濱田さん。令和元年に1回目を開催。令和2年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止を余儀なくされたが、令和3年の2回目に続き、令和4年の3回目には、町内でも認知度が上がり、注目が集まるイベントに成長している。
「『こどものまち』の面白さは、大人が介入しないことで生まれる、ゆるやかな空間であることです。例えば、おもちゃ屋でお金を使い切ってしまう子どもがいても、大人も子どもも面白がることができてしまいます。最も大切にしたいのは、そんな子どもたちを、大人が見守ることなんです。」と濱田さんは話す。


子どもたちを、見守る大人を育てたい!
「『こどものまち』では、大人が子どもたちに対して禁止も指示もしません。大人が介入すると、子どもたちに“ちゃんと”させようとして、軋轢(あつれき)が生まれてしまうからです。子どもたちだけの世界は、ちゃんとしていなくても誰もが優しいんです。どんな店にしたいのか、曖昧なまま当日を迎えても、『こどものまち』ではなんとかなっちゃうんです。」と濱田さん。
一人で参加した子どもが、友達のいないチームにしっかり溶け込み楽しんでいたり、自分たちが参加しているイベントに60 人ものボランティアスタッフが関わっていることに、心を動かされる子どももいたりすると言う。いろいろな年齢の人たちと関わることで、子どもたちは自らアイデアを広げていく。濱田さんは「大人が用意した枠に当てはめる方が、子どもたちの世話をしやすいので、つい先回りして指示したくなります。でも、場所さえ用意すれば、子どもたちは自発的に行動します。そこから何かを得てほしいと大人が望まなくても、子どもたちは必要なものを自然に手にしていくんです。」と話す。
そんな子どもたちを支えるボランティアは、元こども店長や、学生、子育て中の親など様々だ。「こどものまち」は、「ゆるり家」のミッションである「気のいいオトナ」たちが、自然と集まる場になっている。

ひとりの子育てを、地域みんなの子育てに
「いろんな『コドモ』を見守る、気のいい『オトナ』であふれる町をめざす。」
10 周年を機に掲げた、新たな「ゆるり家」のミッションだ。「気のいい『オトナ』」とは、関心を持って子どもたちを見守ったり、叱ったりしながら、地域の子どもたちの子育てに、ゆるやかに関わる大人たちを指す。
「子どもは、いたずらもするし、手のかかる存在です。そんな子ども本来の姿を温かく見守ってくれたり、時にはよその子でも叱ってくれたりする人。多少のいたずらは大目に見てほしいし、ダメだと思ったら、いきなり学校に通報するのではなく、その場で直接注意してほしい。
公民館の前で遊んでいたり、田んぼの畔を歩いていたりするだけで、学校にクレームが入るのは寂しいですよね。」と濱田さんは言う。
20年間続けている子育て支援だが、今、子育て中の母親たちが困っていることは、自分たちの頃と何ら変わっていないことに気づいた濱田さん。「この20年間、何をしてきてたんだろう。」と、思う日もある。
「私たちの頃は、支援してくれる場所がなかったので、当事者同士が地域の中で助け合うしかありませんでした。今は場所が生まれ、保育園の無償化など公的支援が充実したことで、地域の中で子どもの姿を目にする機会が減りました。自治会やPTA活動に消極的な人も増え、余計に地域全体で子どもたちを見守ろうという空気が、薄れていっているようにも感じます。支援してくれる場所はできているのに、『子育ては親の責任』という閉塞感は、変わっていないように思います。」と言う濱田さん。
田口さんは、「世代間のつながりを育て、顔見知りを増やすことが大切だ。」と話す。そのために、子育てを始めたばかりの世代と、同じような経験をした少し前の世代をつなぐ役割を「ゆるり家」が担いたいと言う。「先輩世代は、同じ母親というフラットな立場で『なんとかなるから大丈夫よ』と、気楽に声をかけられる『気のいいオトナ』になってほしい。」
場所を守るだけでなく、ミッションに込めた想いをつないでいくことが、「ゆるり家」の役目でもある。

無理せず、楽しく、恩送りを続けよう
最近、「ゆるり家」では、濱田さんの学習塾や放課後自習室で学んだ卒業生たちが活動に関わり始めている。また、新しく活動を始めた若い母親たちと、世代を超えたつながりが少しずつ生まれようとしている。
今、3人が新しく取り組みたいと思っていることは、地域の公会堂や公民館を活用した子育て広場の開催だ。高齢者向けの活動が中心の施設を活用することで、より多様な世代の人たちとつながる機会が増えるからだ。「公会堂によっといday」と名付けた集いを、すでにスタートさせている地区もあり、「気のいいオトナ」を地域に増やすことを目標にしている。
こうして、「地域の子育て力アップ」をめざし、活動してきた濱田さんたち。「何年、活動を続けることができるかわからないので、NPO法人ではなくボランティア組織を選んだ。」という「ゆるり家」も、14 年目を迎えている。
「活動を始めて間もない頃、初めて参加したお母さんが『ここがあってよかった、気持ちが楽になった。』とおっしゃった姿は、今も胸に残っています。私自身も、手のかかる子どもたちを、みんなに見守っていただき、育てていただきました。お世話になった人へ、直接お返しはできないので、恩送りとして他の人へつないでいきたいと思って、ここまで継続できています。」と佐々木さんが振り返る。
無理をせず、自分たちができる範囲のことを、自分たち自身で楽しもう。周囲の声に耳を傾け、活動の形も中身も柔軟に変化させながら、自分たちがやりたいことを続けよう。「ゆるり家」を守り続けてきたのは、3人の変わらないスタンスだ。
「今からは、自分たちのために、介護のしゃべり場が必要になるかもしれない。」と言う田口さんに、「介護の話はできる!」と佐々木さん。「ここをグループホームにしたら、私も介護してもらえるね。」と笑って答える濱田さん。3人の“気のいいオトナ”たちの明るい笑い声が、いつまでも響いていた。


(取材日 令和4年12 月8日)