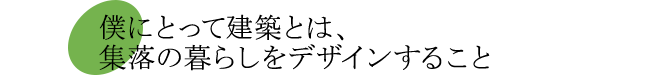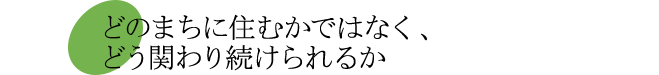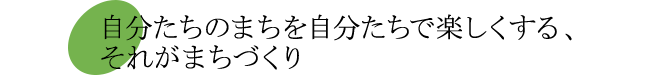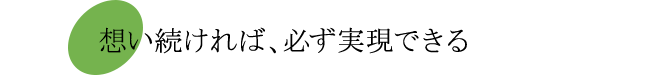「あの時、あの本に出会わなかったら、今、僕はここにいません。」
何万冊という蔵書が眠る大学の図書館で、その一冊は目に飛び込んできた。世界中の集落が集められた、決して厚くはない写真集だった。
「美しいな、こういう仕事に関われるなら一生建築家として生きていきたいなと思えたんです。」
専攻は建築。しかし建物の設計に興味が持てず、大学を辞めようと思い始めた矢先、奇跡のような出会いだった。
「暮らしをデザインすることが建築の仕事なんだ。」
出町さんに、大きな転機が生まれた瞬間だった。
奈良市出身の出町さん。古いまち並みの中で育ったことで「自然と集落が好きになった」と振り返る。
「細い路地を抜けた先で、地元の人たちが立ち話をしている。密集している中にこそ暮らしは感じられるもの。生き生きしていて豊かな気がするんです。」
まちのつくりと環境がリンクしていることも、集落の魅力だという。
「今の日本のまちづくりは、どこも同じで違和感があります。それぞれの場所にふさわしい建物のあり方や暮らし方がありますから、そこに根付く文化や歴史と対話をしながら建築物はつくられるべき。それが集落なんです。」
写真集との出会い、集落への想い。それが数年後、大きなプロジェクトを生み、出町さんのライフワークへとつながることになる。

関西大学建築環境デザイン研究室に所属していた平成18年、空き家を改修・活用したまちづくりの提案が「シナリオ丹波」の丹波市長賞に選ばれた。初めて佐治に来た時、直感的に自分はここに関わることになると思ったという出町さん。建物や観光拠点をただつくっても、地域は元気にならない。自分たちが持続的に関わることが重要だと感じたという。
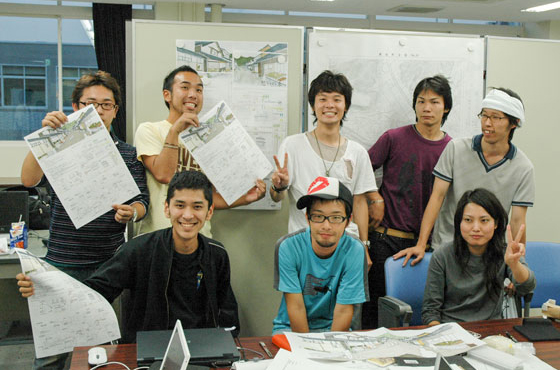
「シナリオ丹波」提案作成していた学生当時の出町さん(一番右)

平成18年、出町さんはコンペの現地説明会のため、初めて佐治に訪れた。
「そこで出てきたのが『関わり続ける定住』という発想でした。」
定住はできなくても丹波を意識して生活することはできる。例えば、今住んでいるところで丹波産の野菜を見つけたら買う、テレビで丹波のことを放映していれば視聴する、大学卒業後もふるさとのように家族と一緒に遊びに来る。「関わり続ける定住」とは、そんな関わりを増やしていければ地域を元気にできるという考えだ。
「住民票を置いて定住しなくちゃ意味がないというのでは、隣町と人口の取り合いになってしまう。『住む』『暮らす』という意味や形がもっと柔軟に広がって、住めなくてもつながってくれるだけでうれしいと伝えられれば、自分がいいと思う地域にもっと気楽に関わり続けられます。」
関わり続ける定住は、大学の活動拠点となる空き家を借りることから始まった。そこで出町さんが最初にしたのは「何もしないこと」だった。
「何の提案もせず、あちこちへ出かけていろんな人と話をしただけでした。まず地域のことを身体で感じた上で、地元の人と一緒に考えながら意見を出すことが大切だと思ったんです。」
草刈りなど日役に参加することで、地域に少しずつ溶け込んでいく。そのうち徐々に理解が拡がり、自分の住んでいる地域を良くしたい、楽しくしたいと思う人が集まり始めた。
「佐治に来たばかりの頃、地域のことを知りたくて小学生に話を聴くと『川で遊んじゃだめ』『通学路じゃない道は歩かない』『将来は大阪や神戸に住みたい、だってゲームセンターがあるから』って言うんです。衝撃でした。都会は優れていて、ここは劣っているという感覚が、子どもたちにあったんです。やばいと思いました。」
空き家活用の理想は、地元出身の人が戻ってくること、ここで暮らしていきたいと思えること。このままでは子どもたちが地元に住んでくれないと感じた出町さんは、空き家の改修に子どもや大人にも参加してもらうことにした。

佐治スタジオの改修は学生をはじめ、地元の子どもから大人まで参加した。
「みんなの居場所、ひみつ基地をつくったらどうだろうって。」
幼い頃のひみつ基地づくりが、誰と、どこで、何をしたかという鮮明な記憶を誰もに残したように、自分たちの場所を自分たちでつくれば、まちへの愛着が深まるきっかけになると考えた。
こうして学生、子ども、大人、みんなで取組んだ居場所づくり。本当に、地元の人がやって来た! 交流会が開かれた! 卒業した学生たちが帰ってきた!
「これが建築なんだ、これが空間をつくることなんだと、楽しさでいっぱいでした。」
地域の人も巻き込めば、おもしろいことが起こっていくのは間違いないと確信した。こうして完成した「佐治スタジオ」は、予想もしなかったさらなる喜びを生むことになった。

現在、バス停の案内に表記されるほど地域に根付いている。
空き家の改修が進んだ頃、「そこにある」もうひとつの意味に出町さんは気づく。それは佐治スタジオに夜、電気をつけた時だった。
「『夜、灯がついているのを見て安心したの。人がいる、ただそれだけで嬉しくて、灯がついたその夜に泣いたのよ』って、向かいのおばあちゃんがお礼を言いに来てくれたんです。あぁ、ここに来て本当によかった。たくさんの人を幸せにはできないかもしれないけれど、少なくとも向かいのおばあちゃんが喜んでくれた。これでいいんだ、関わり続けるだけでいいんだ、関わっていることそのものが重要なんだと思えたんです。感動でした。」
自分たちがそこにただいることで、まわりの人に幸せを感じてもらえることに気付いた出町さん。ささいなことでも重ねていけば、意味のあることにつながること。誰かがやった小さなことが次の誰かに受け継がれ、それがまちをつくっていくこと。それをまちづくりを志す人たちに伝えていきたいと、出町さんは思っている。

毎年関西大学のゼミ生が関西大学のサテライトスタジオとして、「佐治スタジオ」を訪れる。

平成28年より、佐治スタジオの室長は出町さんから植地さん(左)に受け継がれている。
「まちづくりは、今住んでいる人がこれからも住み続けたいと思えるか、暮らしが豊かでしあわせだと思えるかが一番重要です。そういう環境を整えていくこと、地元の人とともに想いを育んでいくこと、価値をつくっていくことが、本当のまちづくりだと思うんです。」
その一環として平成23年、地元住民たちが主体となって活動する空き家活用サークル「佐治倶楽部」を設立。現在60人の会員が参加している。
「最初は、ここで店なんて無理、人がいない、何をやってもダメという声ばかりでした。」
そこで出町さんは神戸の知人に協力を求め、佐治のまちの中心部にある空き家で、かつて薬屋だった「センバヤ」を使って、一日限りの花屋を出店。すると、みんなが声を掛け合い人が集まった。求めている人がいる。青垣でも届く。決して無理なことじゃない。これをきっかけに「空き家でカフェを出店したい」など、利用する人が増えてきた。

「センバヤ」でのゲリラガーデンマーケット。突然の花屋出現は地元で話題になった。
「ないものはつくろう。自分たちでつくれば楽しくなるんです。花屋、朝コーヒーを飲める場所、月末のバー、月に一度のパン屋。佐治倶楽部の活動は、地元の人のためのものです。衣川會舘を改修してからは月に一日くらいは佐治で過ごそう、ここにもおもしろいところはあると発信する場としてキヌイチという活動を始めています。」
「こうすれば地域が元気になる」という答えはない。だからこそ、考えることをやめてはいけない、求めることをあきらめてはいけない。自分たちの手でやれることがあると気づくきっかけを、出町さんは投げ続けている。

月に1度、衣川會舘で行われる「キヌイチ」には、地元の人をはじめ、学生も集まるイベントになっている。

「キヌイチ」では地元で作ったパンをはじめ、卵なども販売されている。

大学生が丹波に1週間滞在し、職業体験等を通じて農山村の現状を知るワークキャンプ滞在型講座が開催されている。
山と田園に囲まれた素朴で美しい風景。温かい人々。このまちで暮らせることが幸せだと語る出町さん。
「今も活動を続けられていることに、感謝の気持ちしかありません。自分を受け入れてくれるこの地域、家族、仲間が財産。幸せです。」
ふるさとの奈良へ帰ると、風景が変わっていることがある。あったはずのものが、そこにない。見慣れた場所がなくなると、地域への愛着も薄れてゆく。
「風景が続いていくことは大切です。風景と地元への愛着は、つながっていますから。まちが空き家だらけになると、地元の人自身も関わるきっかけがなくなってしまう。この佐治のまち並みや風景を大切にしていきたい。建築家として関わっていきたいんです。」
集落の暮らしに関わりながら生きる日々。ずっと求め続けた想いは現実のものになり、出町さんは今ここにいる。

(公開日:H29.05.25)