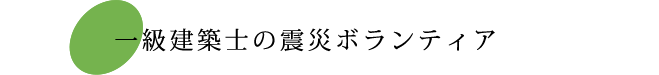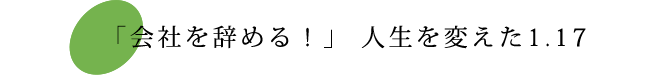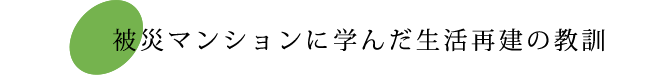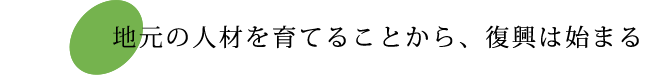野崎隆一さん
平成7年1月17日午前5時46分。神戸市東灘区の自宅マンションで、野崎さんは激甚な揺れに襲われた。幸いマンションは一部損壊で済んだものの、昨日までの穏やかな街はもうそこにはなかった。その後数日間、知人たちの安否確認に野崎さんは神戸の街を自転車で走り回った。
「被災の状況がわかるにつれ何かしなきゃいけないと思い、東灘区役所へボランティア登録に行きました。一級建築士だと伝えると、その場で書類を10枚くらい手渡され、建物診断を頼まれたんです。」
「ジャッキで上げれば大丈夫。」「歪みを戻して補強すれば住めますよ。」相談に答えるたび、行く先々で喜びの声を受け取った。
「見ていただいてありがとう、アドバイスをありがとうって、あちこちで言われるうちにすっかり嬉しくなって、週末のボランティア活動に夢中になっていきました。」
学生時代は建築を専攻し、卒業後は東京のデベロッパー(*)に就職。
「自分たちが企画したまちに、団地を建設して販売する仕事でした。住む人の顔が見えるまちづくりがしたいという想いは、その頃から頭の隅にありました。」
10年後、家業である建材の輸入商社に呼び戻されUターン。しかし設計の仕事への愛着は消えず、テニスや仲間との付き合いでその想いを発散する日々が続く中で起こった震災だった。震災から1カ月が過ぎた頃、野崎さんのもとへある依頼が舞い込んだ。
*デベロッパー:取得した用地に、マンションや商業施設などを企画・開発し事業化する土地開発事業者

平成11年の「1月17日」の前夜に、兵庫区の喫茶店を借り切り、復興課題をテーマにロールプレイを交えて徹夜の議論を行った。

出向いた先で震災を語る「語り部キャラバン」として、平成8年に東京向島のまちづくりグループに招聘され、阪神淡路大震災の経験を伝える活動を支援した。
避難所のひとつになっていた東灘区の小学校で、廊下にまであふれた2,000人近い避難者を家に帰してあげたいという、友人からの相談だった。
野崎さんは、建築に携わるボランティア仲間と共に相談会を週末ごとに開催。専門家たちによる建物診断の結果、アドバイスに従って自宅に戻った人や知人宅に身を寄せた人、社宅への入居を決めた人などが避難所を後にし、2か月間で避難者を700人にまで減らすことに成功。
続けて避難所で開催したまちづくりシンポジウムでは、地区の人々と一緒に「魚崎地区まちづくり憲章(*)」を起案し復興への意志を確認した。
こうした様々な復興に関わる相談が届くようになった野崎さんは、ついに家業である会社を退職することを決意。震災から3カ月が過ぎた4月、建築士として再びまちづくりの世界へ戻っていった。
どんな活動の現場においても、野崎さんは一人ひとりの被災者と向き合い、少数派意見を尊重することを忘れない。その背景には、被災マンションの復興プロジェクトでの苦い教訓があった。
*魚崎地区まちづくり憲章:まちの復興にあたり、住民の共助を目指すことや地元の歴史文化の継承といったまちづくりの方針を11か条にまとめたもの

阪神・淡路大震災の当時の様子や復興までの過程を歩いて学ぶチャリティ・ウォークイベント「こうべi(あい)ウォーク」。平成11年の第1回には、3500人の参加者が集まり、長田から東遊園地まで10キロを歩いた。

第21回目となる今年の「こうべi(あい)ウォーク」には、250人が参加した。
建て替えか、補修か。住民たちの意見が二つに分かれてしまった被災マンションの、合意形成の相談を受けた時のことだった。
それぞれが歩み寄るための話し合いの場を何度も持ち続けたが、努力の甲斐もなく議論は裁判に発展。解決に13年もの時間を要したため、長引いた仮住まいの暮らしで蓄えが無くなったり、ローンの返済が負担になるなどの理由から、戻りたくても戻れない人たちが増え、新しくなったマンションに元の住民が戻ったのはわずか2割だった。
「もともとは親しい間柄の住人たちばかりだったはずです。回り道をしてでも、そんな人たちが少人数で腹を割って話せる場を、なぜもっとたくさんつくれなかったのか。少数派の声と丁寧に向き合うプログラムをつくらなくてはいけないと学びました。自分の命や暮らしを賭けて話し合う機会なんて、めったにありません。多数決だから仕方がないという決め方は、本当の民主主義じゃない。そのことに直面したのが阪神・淡路大震災であり、その象徴が被災マンションでした。」
一世帯一世帯の人生を見なければ、再建はできないと語る野崎さん。
「家を建てることは、生きていく場をつくること。被災者にとっては、自分の人生をどう決めるのかという話です。そこに思い至らなくてはなりません。」
後悔を信念に変え、その後の被災地支援に向かっていた平成23年3月11日、東日本大震災が発生。一週間後に駆けつけた宮城県東松島市の様子を目にしたショックは大きく、神戸に帰るとただちに仲間と「3.11支援集会」の定期開催をスタート。また毎月のように東北の被災地へ通うようになった。

被災から1週間後の3月18日、神戸から知事に同行してバスで現地入りした野崎さんたちの目前に広がった東松島市の惨状。

地域のまちづくりのアドバイザーとして、協力を要請。
「高台移転か、転出か、公営住宅か……選択しろと言われても、まちがどうなるのかわからないままでは答えようがない。」
東北の被災地で、野崎さんは行政の提案に追い付けない住民たちの声に直面した。
「復興がうまくいかない一番の原因は、住民と行政の間に意見のキャッチボールがないこと。行政は住民は答えを返してこないと思い、住民は行政に置いてきぼりにされると思っています。キャッチボールに必要なのは、情報をわかりやすく、タイミング良く住民に伝えること。そのために、今こういう情報が必要だと判断する専門家が存在していることです。」
その専門家の役割を果たすのが野崎さんだ。震災から半年後の被災地では、同じく半年後の神戸の様子を、1年後の被災地では、1年後の神戸の様子をというように、震災からの時間の経過に合わせ復興体験を話してきた。
「阪神・淡路大震災の5年目、10年目、15年目を検証することで、復興の全体像が見え始めていました。震災から半年後は電車が通っていなかったとか、行政が決めた区画整備に『寝耳に水だ』とみんなが怒ったとか、私たちが経験した復興へのプロセスを伝えることができたんです。自分たちのまちがこれからどうなっていくのか、住民たちもイメージができたことで理解も深まっていきました。」
さらに住民たちには、被災した自分たちがどうしたいのか話し合う場づくりを提案した。
「まちづくりとは計画づくりではなく、プロセスづくりです。やってみないとわからないことだらけなのに、修正をしないままプラン通りに進めようとするからぎくしゃくしたり、できあがってみたら自分たちの望んでいたものではないという話になるんです。まちを動かし支えるのは、仕組みではなく人。住民が自分たちで考え、決定し、プランの修正ができて初めて、復興に向けて動き出せるんです。」
神戸の復興を経験した者として、伝えていく責任はいつまでもなくならないと話す野崎さん。伝える責任を、知恵とノウハウとして引き継ぐ機会が訪れたのは、平成28年4月14日、熊本地震の被災地支援だった。

気仙沼市唐桑町只越地区の住民と野崎さん。移転先の選定から関わり、住宅完成までを見届け、住民との信頼関係は揺るぎないものに。

支援した気仙沼市鹿折地区まちづくり協議会では、行政との円卓会議で復興の進め方について理解を深めた。
熊本地震から4カ月が過ぎた頃、野崎さんは南阿蘇村の副村長から一本の電話を受け取った。
「被災した800世帯への相談会を、南阿蘇で開いてほしい。」
そこで野崎さんは、地元の弁護士会やボランティアのネットワーク団体に協力を要請。集まったボランティアたちに、相談会で被災者にヒアリングを行う際の話の引き出し方や進め方、生活再建に向けての制度や補助金についての研修からスタート。相談会が始まると、ボランティア全員で一週間おきにケース会議を開催。誰かがアドバイスに苦慮した相談内容を全員で考え、解決策を導き出していった。
「ボランティアには様々な職業の人が参加していましたが、現場で実際に体験することで人材の育成につながりました。今ではノウハウが蓄積され、その後に起きた西日本豪雨の被災地でも、自分で相談会を開いたという人も現れています。現場が人を育てるんです。」
一緒に活動しながら体験を共有することで、結果的に人材が育つと野崎さんは語る。
「災害が起こると、専門家やコーディネーターを外部から連れてこようとします。一番大切なことは、専門家やコーディネーターが自ら現地で動くのではなく、復興を我が事だと思える地元の人を育てること。みんな地元には人材がいないと思っていますが、育てればちゃんといるんです。」
被災者の人生に関わる覚悟と共に、復興まちづくりに取り組む野崎さん。どんな時も、その視点は人に向けられている。

阪神・淡路大震災や東日本大震災の復興まちづくりの経験の伝達、住民同士の話し合いの場づくりとして「みなみあそ復興塾」を開催。

南阿蘇村での相談会の様子。
「闘うとは、何かを実現するために批判したり、おかしいと声を上げること。争わないとは、そんな場面においても個人的に傷つけ合い、憎しみ合うこととは一線を画すことです。どんなにケンカをしても仲直りはできます。意見が違っても、どこか共通点があるはずです。そこをちゃんと見ない限り、合意形成はあり得ません。」
なぜ相手はそう発言するのか。どうしたら相手の気持ちになれるのか。好奇心にも似た関心を持ち続けることが、合意形成を実現するポイントだと語る。
「成熟した社会をつくるために、いかに地域の住民が中心となって頑張れるか。そのために協議をしてみんなで合意形成を行い、物事を決める。決めたことへの責任は自分たちで持つ。そういう地域に変わっていかなくてはいけません。地域復興に取り組む被災地こそ、その目標に最も近いと思っています。」
楽天家でなくては、まちづくりはできないという野崎さん。
「私は世の中に取り返しのつかないことはないと思っている楽観主義者です。もうだめだと思ったら、まちづくりは終わりですから。私の仕事は、地域という曖昧な概念を相手にしているのではなく、地域に住んでいる人を相手にしています。暮らしや生業は人に付随するものです。地域を単なる場所として捉え、協定や構想をつくって終わらせることはできません。まちづくりには、終わりがないんです。」
阪神・淡路大震災から25年。震災直後、神戸の街にはまちづくりを議論する数多くの熱い場があった。そこから人が育ち、まちを再興するプロセスが生まれていった。復興からの教訓をこれからのまちづくりに伝え継ぐために、あのエネルギーが渦巻く場をもう一度つくる時が来た。野崎さんは、今改めてそう思っている。
 (公開日:R1.12.25)
(公開日:R1.12.25)