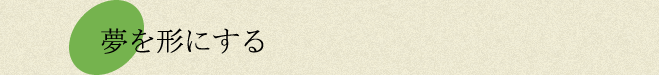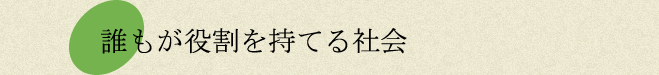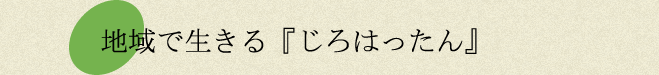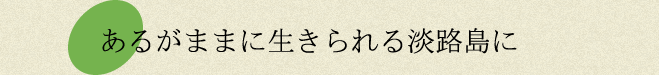淡路島の南、人口約50,000人の南あわじ市。農業、酪農業、畜産業、漁業など第1次産業が盛んだが、島内の他市と同様、若年層の都市部流出や高齢者問題を抱えている。
平成23年、その南あわじ市にひとつのNPO法人が誕生した。「NPO法人ソーシャルデザインセンター淡路(SODA)」は、仕事・役割づくりのためのNPO法人。「だれもが仕事や役割をもち、みんながいきいきと笑顔で暮らせる淡路島に」がキャッチコピー。
理事長の木田薫さんにお話を伺った。

木田さんは、元保育士。出産を機に退職してからも、子どもが大好きで地域の保育所や小学校で絵本の読み語りなど、子どもに関わる活動を続けた。三十代前半から、PTAの活動をきっかけに地区の婦人会長を務めるなど、地域づくり活動に取り組み始める。三十代後半からは、南あわじ市社会教育委員長、市活性化委員長、淡路地域ビジョン委員長などを次々に務め、様々なレベルで淡路島の未来を描くことに携わってきた。
「一度目立ったら、どんどんまきこまれてしまった」引き受けてしまったものは仕方ない、地域のためになるならと、どんな役でも一生懸命に取り組んできたと振り返る。
市の魅力づくりに取り組んだ南あわじ市活性化委員長時代には、長年の地域の夢であった大学の誘致までも実現させた。
SODAの顧問でもある淡路人形協会の正井理事長は、「木田さんは、一見、夢見る少女のようにも見える。でもその夢を具現化していくための道筋を描いているところが素晴らしい。みんなの声を聞いて現状を把握し、分野を問わず的確に課題を解決できる能力を持つ人を見つけてくる。みんなが思い描く夢の場所へみんなを連れて行こうという気持ちが強い」と語る。
今、木田さんが描く夢、それは誰もが仕事や役割をもち、みんながいきいきと笑顔で暮らせる、新しい「しあわせ社会」の実現。その実現をめざして、この地域の将来像を一緒に考え、社会をデザインしていこうとするSODAの取り組みが始まっている。
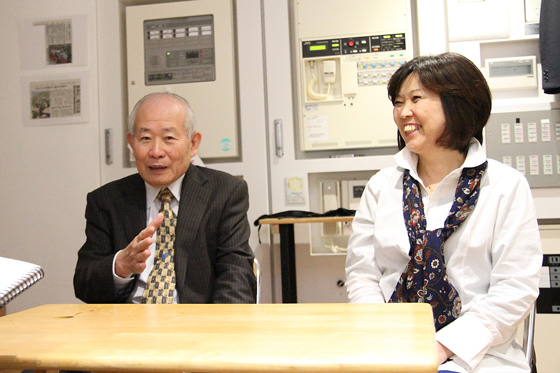
淡路人形協会理事長の正井さんと
SODAでは設立直後から2つの取り組みを中心にすすめてきた。「これからの島のくらしをつくる学校(通称:島の学校)」と、「淡路ソーシャルファーム事業」。
どちらも淡路島に未来の仕事を作っていくことを目指している。
島の学校は、淡路島に暮らす若い人が対象。他地域の先駆的な取り組みを学び、地域で横のつながりを持ってほしいと企画された。
ビジョン委員として5年間、島内をヒアリングして回った時、地域のために何かしたいと考え、実際に行動をしている20代30代の若い人にたくさん出会い、彼らを応援したいと思ったと話す。「学校は、その人の持つ能力や可能性を見出し、引き出すところだと思う。ここに集う人たちが、しっかりと自分探しができたり、共感し合える仲間に出会えたり、もうだめだと思っていた自分のことが好きになれたり…。そしてどんな些細なことでもいいから、明日への一歩が踏み出せるような学校にしたい」
平成25年度は11月から12月の間に4回、計32時間にわたる対話形式の講座を実施。参加者は30代が中心。UターンやIターンの人も多く、参加者同士が互いに刺激を与える場になっている。講師は食を通じて農村部と都市部を結び地域活性化に取り組むフードデザイナー、被災地で地域資源を活用した仕事づくりを進めるコーディネイターなど。いずれも独自の観点から革新的な取り組みを進める人たち。彼らの手法や理念を学び、自分たちの暮らしや仕事を再考する機会にしてほしいというのが、今年の狙いだ。
若い時から「淡路島のお母さん」とあだ名がついていたという木田さん。島の学校を通じて、淡路島の次世代を引っ張っていくような人が出てくれば嬉しいと微笑んだ。

これからの島のくらしをつくる学校‐開校式‐
「淡路ソーシャルファーム事業」では、就労が困難な人たちの仕事づくりという課題に取り組む。
育児中の母親や高齢者、障がい者、社会経験の少ない若者などは、働きたいと思っていても、雇い口がない。就労どころか、社会参加自体を諦めているような人もいる。
「例えば軽い障害を持つ場合、作業自体はできても、長い時間は続けられないようなこともある。そんな人はなかなか安定して仕事に就くことができない。彼らは自分が社会の構成員ではないと感じ、苦しみを抱えている。社会復帰をしたい、と真剣な願いを聞く度に、私はこの子たちが悪いのではなく社会の仕組みが間違っているのだと、憤りすら感じる」
現在ソーシャルファーム事業としていくつかの実験的な取り組みが進められている。
ひとつは本人が無理のない労働時間などの条件を決め、ジョブパートナーと呼ばれる支援者ともに仕事を行うプロジェクト、実際に数人が清掃作業などの仕事に就いている。
その他、育児中の女性による起業グループもある。まもなく、老人ホームの中でカフェ運営が始まるのだという。
「仕事に合わせた人づくりではなく、人に合わせた仕事づくり」を理念にするこの事業。 小さな規模でも、確かな実践例を作ることにより取り組みを広げていきたいと木田さんは語った。
「誰もが社会の一員と感じてほしい。一人でもいいから、誰かの役に立っていると感じられるような、そんな役割や仕事をつくりたい」
そんな木田さんの思いは、学生時代の経験とある本との出会いが原体験になっているという。

真面目にがんばっている子たちの力になれるのが何より嬉しいと話す木田さん
学生時代の実習で行った、精神障がい者が暮らす福祉施設。設備が整い、利用者は生活に必要なほとんどのことをそこで済ませることができるような施設だった。
実習の期間は2週間だけにも関わらず、木田さんはそこに溶け込んでいた。あまりに楽しそうで、まるで木田さんがその施設で生活する利用者のように見えたのだという。いやなものはいや、うれしいことはうれしいという、とても純粋な彼らとの関わりが心洗われるようで楽しかったのだと、振り返る。
実習も終盤に差し掛かったある日、木田さんは一人の利用者から宝物の品々を見せてもらった。周りの職員は驚いて、本当に信頼している人にしか見せないのよ、とその由来を木田さんに語った。それは、その人が子どもの頃、面会に訪れる親から毎年決まってプレゼントされていたもの。入所から数年は続いていたという訪問とプレゼントだったが、ある年突然ぴたりと途絶える。以降、家族からの連絡すらなくなったのだという。
「初めは何から何まで揃って、温かく守られたとても理想的な施設だと思っていた。でも言葉を選ばなければ、まるで姥捨て山。たとえ社会との関わりを絶たれても生きていける場所。果たしてそれは本当に幸せなことなのかと感じた。」
そんな時に読んだのが『じろはったん』。昭和初期の但馬を舞台に知的障害のある青年と、地元の人たちとの交流をつづった物語だ。青年の心優しさや、彼を仲間と思う地域の人たちとの暖かいやりとりが描かれている。
「ああ、私はこういう形がいいなあって、物語の中に描かれているつながりを見て、しみじみ思った」
特別扱いされず、無理もせず、できる仕事を共にする。それぞれが役割を持ち、社会の一員として地域の中で生きていく。「だれもが仕事や役割をもち、みんながいきいきと笑顔で暮らせる」そんな夢の形をその本に見出したのだという。
南あわじ市のあるカフェの店長はこう笑う「木田さんは、ちょっと元気になりにきたーって、お店に寄ってくださるけど、本当は、木田さんが元気を注入しにきてくれるんです」
忙しい日々の中でも、できるかぎり毎日通う、とある老人福祉施設。お年寄り向けに歌いながら、体を動かす体操などのレクレーションを引き受けている。うつらうつらとしていた女性も木田さんの呼びかけに、満面の笑みを浮かべて応える。

特別養護老人ホーム太陽の家でのレクレーション。一人ひとり名前を覚えている木田さん
他にも、人形劇団や絵本の読み語りなどで忙しく島内を駆け回る。
「みんなに笑ってもらってなんぼ」と考えている。笑顔の力を実感したのは阪神・淡路大震災の時だった。
被災して2週間が立ったころ、北淡に住む友達から一本の電話がかかってきた。「みんな笑うことができない。木田さん、あなたの笑顔を持って来てください」何ができるかと迷いながらとるものもとりあえず、劇団の仲間と二人、人形劇の用意をし、避難所となっている体育館へと向かった。
中へ入ると広がっていたのは、寒々とした空間。たたまれた布団の山と、不安顔の子どもたち。そして背中を向けて寝転がる疲れきったお年寄りだった。
「冬の冷たさじゃない、冷たさがあった。子どもたちもぎゅっと表情をこわばらせていて…」木田さんの古くからの友人で、劇団活動を共にする稲室さんは振り返る。
とても劇をするような雰囲気ではないと、二人はひるんだが、なんとか気持ちを奮い立たせ用意した劇を始める。人形を動かし、歌う。
進めるうちに、一人、また一人と少しずつ顔をこちらに向け始める。ちょっとずつ顔に笑みが浮かぶようになる。
「最後には、にいちゃんねえちゃんありがとう、また来てなって声かけてもらって。次は星影のワルツ歌ってなぁってリクエストまでもらった」足元にしがみついて離れない子どもたちをなだめ、おじさんたちに見送られ、体育館を後にした二人。車で帰る道すがら、一日を振り返りながら、共通の思いに行き当たる。
「人が苦しい局面で、芸術とか文化って役に立つんやなぁ。役に立つのならできることをやらなきゃね」

「絵本の読み語りもいろんな世代に対して続けてきた。小さな子どもも、高校生も、おじさんも涙する。みんなそれぞれにしんどいことがあるよなぁって思う。自分にできることでそうした気持ちに寄り添っていきたい」
自身も図書館で、絵本や物語を見ながら、1時間2時間過ごし、気持ちを楽にすることもあるという木田さん。お気に入りの絵本をひとつ教えてくれた。かばくんが、いろんな職業に挑戦しては、失敗を繰り返すお話はこう締めくくられる。「ぼちぼちいこかということや」――――

「島もこの社会全体も、抱える問題は多い。でもマイナスのことばっかり言っていてもおもしろくない。パワースポットじゃないけど、つまずいたり、悩んだりした人が来れば元気になれるそんな『淡路島』にしたい」
誰もがあるがままに生きられる、そんな島をみんなの手で。

(公開日:H25.11.25)