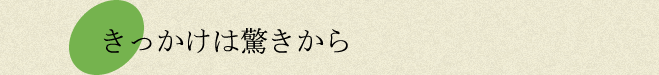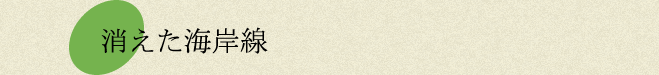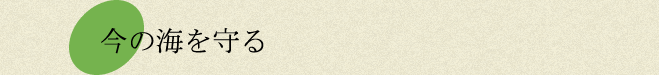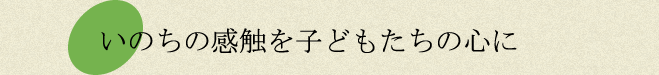播磨臨海工業地帯の中核を担う高砂市。その昔、遠浅で子どもたちの遊び場となっていた海岸は、戦前から高度成長期にかけて埋め立てられ、今はそのほとんどを大規模工場が占める。
そんな薄れゆく高砂の海の存在を、今の子どもたちにも身近に感じて欲しいと活動を進める人がいる。
播磨マリンクルー代表吉政静夫さんに話を伺った。

高砂市内の全ての小学校で、2年生の授業の一環として実施されている「出前水族館」。ボランティアグループ「播磨マリンクルー」が提供する体験型プログラムだ。
代表の吉政さんが平成14年から、高砂の子どもたちに高砂沖の海の生き物に触れる機会を提供したいと始めたこの活動。現在は70歳代が中心のメンバー20名で活動に取り組む。小学校以外でも保育園や幼稚園、地域イベントなど各地へ出かけ、精力的にプログラムを展開している。

播磨マリンクルーの出前水族館は、海水を張った直径1メートルほどのたらいに、高砂沖の生き物を放し、子どもたちが直接触れるというもの。
マダコ、イイダコ、ハリイカ、アカエイ、アナゴ、ヒラメ、ヒトデ、ナマコ、ワタリガニなど、そのほとんどが当日の朝に高砂沖で捕れたものばかりだ。
子どもたちはおじいちゃんやおばあちゃんのようなメンバーに見守られながら、普段触ることのない生き物に触れる。
持ち上げた手に吸い付いてくるタコの吸盤に歓声を上げる子。エイを裏返し、おなか側についている鼻と口を興味深そうに見つめる子。ぬるぬると手をすり抜けるアナゴの持ち方を教わり、四苦八苦しながら何度も持ち上げてみようとする子。メンバー手作りの専用コースを横走りするカニのすばやさに熱狂する子――
「あちらこちらできゃーっと声が上がり、きらきらと目が輝く。体全体で喜びを表してくれるので見ていてこちらも楽しい」と吉政さんはにこにこ。
また、切り絵づくりや折り紙、音遊びなどの体験プログラムも一緒に実施される。
切り絵や折り紙は「海の生き物」がテーマ。目の前でメンバーが作るタコやカニを手本にして、たらいの中の実際の生き物も観察しながら、子ども達は作業を進める。うまく完成させるためには、細部にわたってその生き物の特徴を掴まなければいけない。そのため子どもたちは目を皿のようにして生き物を観察する。

メンバーそれぞれの特技を活かして切り絵や折り紙などに取り組む。
貝殻を擦り合わせたり、耳にあてたりして音を楽しむ音遊びは、海の近くに育った昔の子どもならごく当たり前にしていた遊びだ。
メンバーたちの特技を生かしたこれらのプログラムは、子どもたちが五感を余すことなく使い、高砂の海やそこに生きる生物をより深く知るための工夫が凝らされている。
昔なら海辺で遊ぶことにより自然に体験できたことを、今の子どもたちに提供しているのがマリンクルーの活動だ。
開始から10年間で延べ3万人もが体験するまでに広がった播磨マリンクルーの出前水族館。
もともと、吉政さんは水族館のスタッフでもなければ漁師でもない。業務用特殊糸ノコの製造販売を行う会社の経営者だ。海と直接関わりのない仕事をしてきた吉政さんがこのような活動を始めたきっかけは、ある出会いにあった。
60代も後半にさしかかった頃のある日、いつもの飲み屋で近くに座った漁師と意気投合する。その漁師から「これ高砂でとれるんやで」と見せられたのが、タツノオトシゴだった。
子どもの頃、毎日のように海に遊びに行き、高砂の海の幸も口にしてきた。そんな身近な海にまさかタツノオトシゴのような珍しい生き物が暮らしているとは思ってもみなかった吉政さん。驚きのあまりその場で譲り受け、自宅で飼育を始めた。
丸めた尾っぽにつきだした口。そのかわいらしさを感じながら、日々世話に勤しんでいくうちに、カメラ好きだったことも手伝い、こまめにその姿を写真や動画に収めていた。
そんな時、タツノオトシゴの生殖活動や出産シーンの撮影に成功した人は数少ないという話を耳にする。「そもそも人にできないことに挑戦することに、何よりもやりがいを感じる性格。この年にしてこんな珍しいことに挑戦する機会が巡ってきたんだとわくわくした」
度重なる失敗にもめげることなく撮影に取り組み続けた末のある満潮の日。やっとの思いで生殖から出産までの貴重なシーンを映像に収めることに成功した。

「海の生き物も犬やネコのように人に馴染む」この子らがかわいくてしょうがないと語る吉政さん。
撮影に成功した例は世界的にも数少ないとあって、マスコミの取材が相次いだ程の貴重な映像。これを使って、自分自身も驚かされた高砂沖の生き物の豊かさを、多くの人に伝えたいと思い立つ。特に子どもたちに、自分たちのふるさとにそんな豊かな海があること伝えたいとの一心で活動をスタートさせた。
しかし実際にやってみると、映像を見せるだけではその感動はなかなか伝わらない。
「子どもたちにダイレクトに伝えるなら、匂いや感触を通じた実体験の方が良い。なんといっても本物を見せてやりたかった」と、漁師に売り物にならない魚や生き物を譲ってもらえるよう交渉し、近所の小学校などで出前水族館を試みた。
当初は1人で始めたものの、評判も手伝って出前の回数が増えだした頃から、仲間探しを始める。以前通っていた高齢者大学の同級生らにそれぞれの特技を生かしてほしいと声をかけ、まちで見かけた切り絵の名手を口説き落としたりもした。
こうして賛同する仲間たちとともに播磨マリンクルーを結成。さらに仲間を増やしながら、今の出前水族館を作り上げた。
吉政さんが撮影に成功したタツノオトシゴの出産シーン
播磨マリンクルーの中心メンバーは高齢者が主で、また生粋の高砂っ子が多い。彼らは心のなかに、同じ原風景を共有している。それは毎日の暮らしとは切っても切り離せない高砂海岸の風景だ。
昔は海岸がすぐ手の届く場所にあった。高砂の子どもたちは学校が終われば家にかばんを置いて、すぐ海へと飛び出していった。
「家におもちゃなんてないから、日が暮れるまで海で遊んでいた。自分で竿を作って魚釣りしたり、遠浅の岸を足でさぐってアサリをとったりと、海でならいつまでも遊んでいられた」

副代表の古川さんも、高砂海岸には多くの思い出を持つ。
しかし、そうした風景が見られたのは昭和30年頃まで。その後高砂の海岸は、産業の発展とともに広範囲が埋め立てられ、海岸線はその分南へと遠ざかった。その距離約1km。子どもたちが学校帰りに遊びに行っていた海辺は消えた。
「自分たちの遊び場だった砂浜が埋め立てられていくところだって、僕達は見ていた」
パイプを使って沖の海底の泥を吸い上げ、その泥で埋め立てられていった砂浜。子どもたちは、泥の上に一人寝られるほどの板を渡し、その上に乗って泥に交じるうなぎをとっていた。怒られながらも、みんなやめなかった。単純におもしろかったのだ。
「その時は分かっていなかったけど、それは二度と海辺で遊べなくなるということと引き換えの、最後の遊びだった」
これ以降、日常的に海辺で遊ぶ高砂の子どもたちの姿は見られなくなった。
昔の海岸線がどのあたりにあったのか、今の子どもたちの親だって知らないと話す吉政さん。ふるさとの海岸の記憶を持つ人は、ずいぶんと少なくなっている。
今では、大きな工場が立ち並び、トラックが行き交う道路を超えた先にある海。子どもたちは海に近づくことすら容易ではない。
すっかり遠くなった海岸だが、海岸線に設けられた県立高砂海浜公園に砂浜が残る。
といっても、埋め立てられた際に作られた人工の砂浜だ。ここが今の高砂っ子にとっての、唯一の海との接点となっている。
近年ここでアオサの異常発生が続き、アサリなどの干潟生物を脅かし、悪臭の原因ともなっている。
子どもたちのために地引き網漁を企画した吉政さんもその惨状に頭を悩ませた。
しかし、ここでもチャレンジ精神が燃え上がる。吉政さんは地域住民に呼びかけて高砂海浜公園海辺の保全集いの会を結成。アオサの回収を地引き網漁の体験とセットにして、子どもたちも一緒に清掃活動を楽しめるイベントに変えてしまった。
平成24年9月に行われた第1回目には約120人が参加。1時間程度で、買い物カゴ100個ものアオサが集まった。
翌年も月に1度ほどのペースで、地域住民、子どもたちを巻き込んで海岸のアオサ回収を実施。地域住民が海に触れる貴重な機会ともなっている。

県立高砂海浜公園で行われた「アオサお掃除大作戦」。
明石高専と協力し、アオサを使った堆肥づくりにも取り組む。
吉政さんに協力する漁師の山口初雄さんは、「高砂には海があることを、ちゃんと思い出してもらえる、そして子どもたちに高砂の海のことを伝える機会をつくってくれることがありがたい」と活動に寄せる思いを語った。

高砂港にて山口さんと吉政さん。山口さんの船で底引き網体験も実施したことがある。
吉政さんの活動は、埋め立て地の工場を取り払い、海岸線を昔の位置に戻すことを目的とするものではない。時代や暮らしが変わっていく大きな流れの中で、どうしても取り戻せないものはあるのだと話す。しかし、だからこそ今あるもので、今できる形で、ふるさと高砂の海をより身近に感じてもらいたい、そして海の体験が子ども達のふるさとの思い出となるような取り組みを続けていきたいのだという。
「今の子どもたちがかわいそうだと思うのは、自然との接触がないこと。生き物たちとふれあい、命と向き合うという体験をする場があまりにも少ない」
出前水族館で、悪気なくアナゴを折り曲げ、死なせてしまう子もいる。海中に生きるものは、海水から取り出すだけで刻々と手の中で弱っていき、ほどなく命が絶えてしまう。中にはそれを想像すらできない子どもたちもいる。
五感で命を感じ、自分以外の生きているものとどのようにつきあうか。手に残る感触や匂いとともに、生の体験として心に刻む。子どもらが成長し社会を支える側に立った時に、きっとこの経験が何よりの糧となるはず。吉政さんはそう信じている。
吉政さんがいつも肝に命じている言葉は「何事も一生懸命」。
自分を育ててくれたふるさとの海。孫世代へもその豊かさを伝えたいと一生懸命に活動に取り組む。

(公開日:H25.12.25)