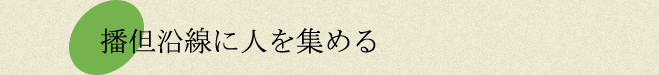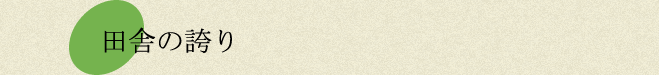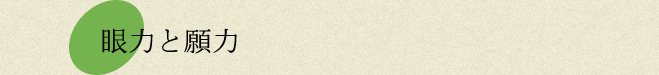古くから駅前を中心にまちが発展してきたJR播但線沿線。時代が移り、鉄道利用者が減少するなか、改めて地域のシンボルとして駅前を見つめ直し、魅力の再発見に取り組む人がいる。
播但沿線活性化協議会代表小野康裕さんにお話を伺った。

平成25年11月3日、小雨が降るJR播但線寺前駅前。神河町観光協会主催の収穫祭イベントの中で、あるトークイベントが行われた。
その名も「駅前トーク」。住民が駅前に集まり、駅前地域のあり様を住民どうしで議論して、地域の活力に繋げていこうという趣旨で、播但沿線活性化協議会が企画した。フォーラム形式のトークイベントで、播但線の各駅で行われる様々な催しに合わせて開かれる。今年は8駅での開催が計画され、寺前駅は7駅目の「駅前トーク」となった。

寺前駅前での駅前トーク
「駅前トーク」では、小野さんが進行役を務め、姫路市在住の版画家、岩田健三郎さんと地元代表者が、駅や周辺についてのトークを進める。開催駅によって、地元代表者は地域住民であったり、役場職員であったりと変わるものの、岩田さんは「よそもの」という立場で全ての駅前トークに登壇。播但沿線各駅全てをまわり、駅ごとのイメージを表現した版画作品と、駅周辺の地図を描いた岩田さんは、地元とは違う視点でその駅を語る。
知人でもいないと来ることがないようなローカルな駅ばかり。駅前トークではよそものの観察眼を借りて、地域の人たちに駅前の魅力の再発見を提案する。

岩田さんの地図がまとめられた播但線各駅停車案内は、早々に在庫がなくなってしまった。
そんな「駅前トーク」が始まったのは、「なごやか甘地地域づくりの会」が平成20年に始めた「甘地駅前ビアガーデン」がきっかけ。甘地駅前のJA支店跡に突如現れる、夏の一夜限りのビアガーデンだ。地元住民の通勤や通学に利用されてきた甘地駅。会場の至るところで昔の駅前についての話が始まるのだという。「昔は、みんな駅までは自転車。どの自転車置き場が安かったとか、駅に至るまで最短ルートをいかにして見つけ出したかとか、そんな地元ネタだけでそこかしこが延々盛り上がるんです」と小野さんは笑う。
この年に一度のビアガーデンは、小野さんの発案。
家業の野菜苗の生産卸業を継ぎ、30代前半から社長業を務めていた小野さん。仕事や青年会議所の活動などで国内外を飛び回っていたが、消防団OBの友人らから地元の活動へそろそろ本腰を入れてほしいと依頼されたことがきっかけとなった。

なごやか甘地地域づくりの会の則正さんと村田さん。小野さんを誘った消防団の友人たちだ。
JA支店の撤退とともに寂れてしまっていた甘地駅前。利用客のほとんどは駅まで車を使ってやってくるため、今の駅前は単なる通過点となってしまっている。
年に一度でもいい。駅前に集い、語り合い、つながりを深める場所ができれば、地域の活性化の足がかりになるのではないか。そうして小野さんは人が滞留する仕掛けとして、甘地駅前ビアガーデンを考えだした。最初の年の準備期間は1週間だったにも関わらず、地区人口の1割ほどの300人を集める盛況ぶりを収めた。
そして翌年以降は、単に飲み語り合うだけではなく、文化的な要素も取り入れた試みが始まる。JAの旧金庫室を舞台にしたジャズ演奏会。古い写真などを集め、有志が製作した「甘地地域今昔物語」の上映。集まった人の思い入れをもり立てるような仕掛けがなされた。「よそもの」の岩田さんを招く「駅前トーク」もその一環として始まった。
初めは3年限りの予定だったビアガーデン。あまりの評判の良さに、継続が決まる。
そして5年目を迎えた平成24年。こうした催しが播但沿線各駅でも行われればおもしろいのではないかという声があがる。それを受け、甘地駅がある市川町に加え、沿線の姫路市や福崎町、神河町の有志が集まり、播但沿線活性化協議会が発足。新たなイベントを立ち上げるのではなく、既存の地域イベントと合わせて「駅前トーク」を行う方法により取り組みを広げていくこととなった。
「それぞれの駅そのものはありきたりでも、そこに寄せる人々の思いはありきたりではない。思いは、よそ者にとってはやってくる動機となり、地元の人にとっては守ろうとするという原動力になるようなもの」そんな思いをいかにしてわきたてるか。小野さんはそのための仕掛けをしているのだという。
地元の人々が、意図して、心がけて守らなければならないもの。小野さんが現在会長を務める「食・地の座」の活動も、そんな意味合いを持つ。
「地の者が、地のモノを、地の人に届ける」がコンセプトの食・地の座。
毎年、播磨の食材を使った新商品開発を行い、年1度姫路の酒蔵で開催される「味覚の展示場」において大々的に発表する。昭和30年代の酒蔵が立ち並ぶ敷地内で、食・地の座のメンバー30社ほどが出展。会場内では新商品を含め、様々な地元食材を使った食品やお酒が販売される。2日間に渡り約6,000人が訪れる、にぎやかな食のイベントだ。

味覚の展示場
食・地の座のメンバーは、播磨地域の農水産業、食品加工・販売業、酒造業や飲食店などを家業とする人たち。ファストフードやチェーン店の流入により、地域の多様な食文化の均一化や、それに関わる地元産業の行く末を案じ、活動が始まった。
昨年度は「播いて磨く播磨地の塩」がテーマ。出展メンバーは、播磨の海水を原料にした塩づくりからスタートし、それを使った新商品を開発した。
10年目を迎える今年からは、認定商品制度も導入。食・地の座ブランドとして、より広くアピールしたいという考えだ。
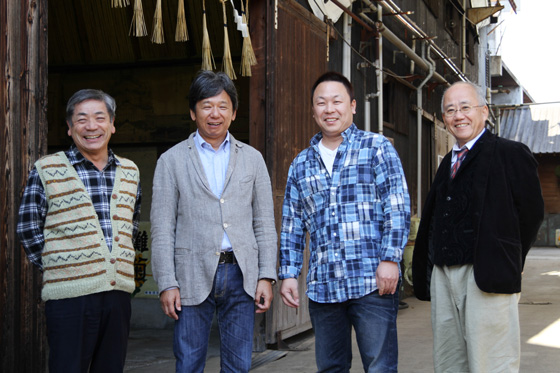
左から展示場会場となる灘菊 川石社長、小野さん
食・地の座の事務局でプーレまつもと 松本社長、エルデベルグ平井 平井社長
「新商品が売れることで地域が活性化されるのではない。地の物を使った商品開発をすることで、地域の産業全体の活力が上がっていく」と食・地の座のメンバーは考える。
地域の食文化を守り、育てていくためには、生産から加工、販売、流通に至るまで、それに関わる全ての者が地域の産業を支えているという意識が不可欠なのだ。
小野さんは言う。「今までなら中間業者に任せていれば済んでいたようなことを、自分たちで考えなければいけないのです」
参加する企業の規模もそれぞれ違う食・地の座。お互いに刺激を与える会になっている。
小野さんは、英国王立園芸協会の日本支部の立ち上げにも関わるなど、ヨーロッパへの造詣も深い。実は自身の地元について考えを巡らすようになったのは、ヨーロッパの「田舎観」に新鮮な驚きを感じたからだという。
視察でイギリス全土を巡った時のこと。ケルト文化の香りを色濃く残すウェールズ、ガーデニングで名高いコッツウォルズなどを訪れ、小野さんは驚いた。田舎とされるような地方で、自給自足の生活を送る人たち。彼らには、田舎を否定したり、都会と比べて卑下するようなことなどはみじんもなかった。むしろその歴史と文化に誇りを持って語る。そんな姿に感銘を受けたのだという。
それとくらべてみて、自分には語るものがない。
「海外でいろんな人とコミュニケーションを取るときに、自分の国や故郷の知識がなかったり、きちんと語れないと思いは伝わらないんです。さすがに英国人の三島由紀夫おたくから、彼はなぜ自害したんだと思うって訊ねられた時には、閉口しましたけど」
その土地に伝承されている文化を意識すること。ただし、そんな「文化」は気に留めなければ、自分たちでは気づかない。「私は野菜を育てる方法も、そこに根付く文化のひとつだと思います。その土地に合った独自の工夫が地域や各家庭に息づいている。家庭菜園の方法が親から子へ受け継がれること。それも文化伝承のひとつだと考えます」
いつもは見逃してしまうものや、目に見えない思い入れの部分を、自分たちの文化として認識し、誇りを持たせる。欧米のように自らの文化を他者に語るためには、自分たちの気付きとそれに輪郭を持たせる工夫が必要だ。
ビアガーデンも駅前トークも、そんな気づきをもたらそうとする小野流演出のひとつなのだ。

播但沿線活性化協議会は今、サイクルトレインを提案している。
サイクルトレインとは、自転車をそのまま鉄道車両内に持ち込むことができるサービス。
今のルールでは、列車には、自転車をそのまま持ち込むことはできない。そこを変えてみたいのだと小野さんは語る。
「播但沿線には、銀の馬車道もあります。降りる駅やどこへ向かうかによって難易度が変化するようなサイクリングコースも提案できるでしょう。もし自転車を気軽に載せることができれば播但線を降りた後の行動範囲を、がらっと変えられると思いませんか?」
おもしろくなかったら田舎なんて埋没するしかなくなってしまう、おもしろみを持たせるような仕掛けをしたいのだと語る。
「もちろんJRさんの協力も必要になりますし、なかなか難しいとは思います。ただイベントとしては前例もあるし、まったく無理なことでもない。環境配慮や健康の観点から見た時に、移動手段として徒歩や自転車の比重があがるのは明白。今取り組めば先駆けになれると思いますよ」

座右の銘は、「眼力」と「願力」。見極める目と、願い思い続ける力。その2つは持ち続けようと、心に決めているのだという。必要だと考えれば、組織でもやり方でも躊躇なく既存の形を変えていく。それだけに理解されないこともあると小野さんは言う。それでも思い描いた先のことをあきらめることはなかった。
優しい目で見据えるその先に、まだ小野さんが追い求めるものがある。

(公開日:H25.11.25)