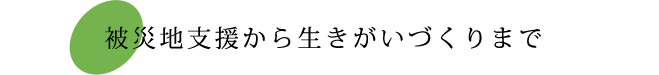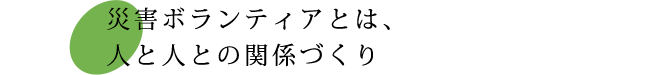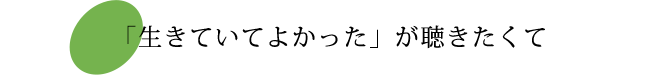社会支援制度の仕組みからこぼれ落ち、見過ごされがちな社会的弱者へ、やさしい眼差しを向ける頼政良太さん。原点となったのは、学生時代に携わったホームレス支援でした。
「真面目に働きたくても住所がなくては仕事に就けない、仕事がないと住居が持てない。どんなにいい人でも、世間の仕組みからちょっとこぼれ落ちてしまったら、なかなか元の暮らしに戻れない。うまく生活できない人たちが、もっと暮らしやすくならないか。」
「最後の一人まで」をモットーとして、人と人との温かい関係を紡ぐ災害ボランティアとして精力的に活動を続ける頼政さんに、お話をうかがいました。
「今まで自分は、災害のことを何も知らなかったんだ。」
まっすぐ歩いているはずなのに、傾いた家々が体の平衡感覚を奪っていきます。平成19年5月、石川県能登半島の被災地に立った頼政さんは、初めて目の当たりにした災害現場の光景に、大きな衝撃を受けました。
頼政さんが災害ボランティアの道に進んだのは、大学入学後、ボランティアサークルを見学したことがきっかけでした。学生たちが能登半島地震の避難所で取り組んだ足湯ボランティアの活動報告を、周囲の人たちが「足湯は素晴らしい!」と感想を述べる様子に疑問を感じました。
「お湯に足をつけるだけなのに、何がそんなにいいんだろう?」
経験してみればわかるかもしれないと、頼政さんはサークルのメンバーとして被災地へ足を運び、足湯ボランティアの活動を体験。高齢者たちに喜ばれ、2度目の訪問では指名されるほど仲良くなりました。
「交流することに意味があるのだとわかったんです。助けに行くのではなく、交流を通じて被災地の方々から学びをいただくのだと、感じるようになっていきました。」
大学3年生になる頃には、被災地で活動する団体への就職を視野に入れ始めた頼政さん。サークルの見学を通じて知った恊働センターでアルバイトを始め、およそ半年が過ぎた平成23年3月、東日本大震災が発生。頼政さんの大きな転機になりました。
「東京へ行ってほしい。」
被災地の復興支援プロジェクトの一環として日本財団が取り組む、足湯ボランティアの事務局を恊働センターが請け負うことになり、その担当者に抜擢されたのです。
「ボランティア希望者をバスに乗せ、東京から東北の被災地へ送り届ける業務でした。目指したいと思っている世界へ行くためには、現場での経験値を高めることがプラスになります。さらに、東日本大震災という国内最大級の災害で、何もできなかったと後悔するより、休学して参加しようと思ったんです。」
初めて経験する津波被害、あまりにも広大な被災エリアなど、何から手を付ければいいのかさえわからない状況に、これまでの自分の活動では通用しないことを実感。もっと経験を積まなくてはいけないと感じた頼政さんは休学していた大学を退学し、正社員として恊働センターへ就職しました。
2年間の東京でのプロジェクトを終え神戸に戻った3年後の平成27年、恊働センターの2代目の代表に就任。自分なりのカラーを模索し続けながら、様々な事業を展開しています。

能登半島にて、仮設住宅で行われた足湯ボランティア活動

恊働センターでのアルバイト時代に、佐用町で森林整備をしている頼政さん
恊働センターの活動の一つが、災害発生時に被災地へ入り支援を行う「災害救援事業」です。プロジェクトの立ち上げやボランティアスタッフの手配、時にはボランティアセンターの運営に携わるなど、被災地での調整役を果たします。
被災地支援と同時に力を注ぐのが復興支援。障がい者サポートやまちづくりをはじめとする様々な分野から講師を招き、勉強会を開く「寺子屋事業」を行っています。
「復興期は災害に特化した支援より、日常を取り戻していくことが大切です。がれきがある、泥が入ったというのは災害による被害。そこから通常の生活を取り戻すプロセスにおいては、災害の知識以上に日常のことを知らなければ支援できません。例えば、災害により雨漏りを起こしている家がもともとゴミ屋敷だったら、災害とゴミの問題には境目がありません。雨漏りを直すだけではなく、ゴミをどうするかなど日常的な支援方法も考えたプランニングが必要になります。」と話します。
そうした復興支援の一環として取り組んでいるのが、「まけないぞう事業」。阪神・淡路大震災をきっかけに、被災者の生きがいづくり・仕事づくり事業としてスタート。「一本のタオル運動(*)」で集まったタオルを、被災者が象の形をした壁掛けタオルに作り変え販売しています。
「東日本大震災の後、うつ病になった女性が、まけないぞうづくりで笑顔が出始め、うつ症状が改善されたケースがあります。購入した方から『私も頑張れる』と手紙が届くことで、自分には元気を届ける役割があるのだと感じ、元気になっていかれました。」
さらに、こうした様々な活動を通じて抽出した、災害時の課題を解決するため、広く市民に向けた「提言・提案活動」も行っています。阪神・淡路大震災20周年および25周年ではアクションプランを作成し、災害時の課題解決について高校生や大学生と一緒に考えました。
これらの事業に取り組む上で、頼政さんが一番大切にしているのはコミュニケーションだと言います。
*一本のタオル運動:平成9年1月に発生したロシア船籍タンカーの座礁事故の際、流出した重油を拭うため全国から膨大な数のタオルが届いたことをヒントに、新品タオルの送付を全国に募った企画。

車座によって行われた勉強会「寺小屋」

ゾウの壁掛けタオルをつくる「まけないぞう事業」で被災者を支援
「足湯ボランティアに取り組んでいた学生時代、がれきの片づけを行っているボランティアの方から『おまえは足湯の活動ばかりで、災害現場を知らないからダメだ』と言われたことがありました。確かに体験していなかったので、やってみたんです。ドロドロになったタンスやアルバムも、被災者にとっては思い出です。その思い出を捨てなくてはいけない作業なんです。大切なことは、早く片付けることではなく、少しでも辛い思いをしないよう、その人のペースを大切にすることだと実感しました。それは被災者とコミュニケーションを取らなければ、わからなかったことです。」
災害ボランティアとは、「この人が来てくれてよかった」「この人のおかげで、また前を向ける」と被災者に思ってもらえるような、人と人との関係づくりだと確信した頼政さん。同時にコミュニケーション不足により、見過ごされている問題もあることに気付きました。そのひとつが、支援制度の仕組みからこぼれ落ちてしまう人たちがいることでした。
例えば、要介護認定がおりない中、認知症により物事の判断ができにくくなった高齢者。食事も満足に摂れない中、仕事のため日中の支援イベントに参加できない母子家庭の母親。住居確保の支援を受け就職したものの、再び職を失い途方に暮れる生活困窮者など様々です。
「法律や仕組みによる支援条件に当てはまらない人はしょうがないと、取り残されてしまうのが多数決。声も上げられない人たちに目を向け、代弁者になろうという意味で『最後の一人まで』を、恊働センターのモットーとして掲げています。」と話す頼政さん。
「制度で救えるなら制度で。制度が無理なら近所づきあいで。それも無理ならボランティアで。いろいろなセーフティネットの中の、どれかに当てはまればいい。いろいろな人が、いろいろな方法で手を差し伸べてくれれば、最後の一人まで支援が届くはずです。」と言います。
「鳥の目だけで全体を俯瞰し網を投げたのでは、最後の一人はこぼれてしまいます。虫の目になって一人ひとりの状況に合わせ、できることを行っていく人も必要です。鳥の目として取り組む行政にはできない部分を、私たちが虫の目になり力を合わせていければいいと思っています。」
最後の一人を取り残さないために、頼政さんは歩みを緩めることなく挑戦を続けています。

被災地では地元ボランティアたちと今後の支援について相談を重ねる

ボランティアの皆さん
平成30年から、頼政さんは大学院で被災者支援の研究に取り組み始めました。
「経験が大切だと思って積み重ねてきましたが、ある時、その経験が邪魔になると思ったんです。災害の現場は一つひとつ異なるため、解決方法に正解はありません。しかし経験を積むほど、私が提案する方法が正しいと思われるようになっていました。自分が正解を出すかのように経験を伝えるのではなく、もっと研究をしてみようと思ったんです。」
頼政さんには、研究したい多くの課題があります。一つは、被災者が自分でできることに、自分自身で取り組めるようになることです。
「支援方法ばかり議論しがちですが、被災者も自分でできることはたくさんあります。それなのに、ボランティアが来たことによって自立の機会を逸したり、可能性を見失ったりするのではないかと思っています。ボランティアと被災者といった垣根を超え、一緒に取り組める方法がないか考えているんです。」
二つめは、災害と日常の境目を乗り越える方法です。
「例えば、被災後に生活している2階を片づけて欲しいと頼まれた時、災害支援以外は手を出せないのでは、その人が困っている状況は変わりません。解決するためにボランティアがどう役立てるのか、災害と日常の境目になだらかなぼんやりとした境界線が引けないか、理論的な研究を通じて可能性を見つけたいんです。」
そして三つめが、できないことより「できること」を見つける視点です。
「災害時は、キッチンが壊れて食事が作れない、車がないので移動ができないなど、被災者の『できない』ことばかりを見てしまいがちです。そういう状況の中でも、『できる』ことを見つけられないか、できることを集めたら、できないことをカバーできるのではないかと思っています。」
こうして日々、被災者に心を向ける頼政さんの原動力、それは「災害に遭ったけれど、生きていてよかった」と、被災者が思った瞬間を感じ取れることだと言います。
「例えば、『災害後、料理をする気が起こらなかったけれど、自分でカレーをつくってボランティアの人たちに食べてもらった』と言われた時は、本当にうれしかった。被災された皆さんが、少しずつでも前を向いて進もうと思える瞬間に関われることが、ありがたいと思っています。」
最後に聞いてみました。頼政さんのカラーは、見つかりましたか?
「カラーが変わるのが、私のカラーだと思っています。被災者ができない部分は支え、できることは自らの力で取り組んでもらう。そんな環境をつくるためには、その場その場でいろいろな行動を起こさなくてはいけないので、言うことが変わる場合もありますが、被災者が自立するためならやり方にこだわりません。いろいろな意見を集め、いろいろなボランティアたちの可能性を信じること。そうすれば、被災地は支援できると思っています。」
(文/内橋麻衣子 動画/三好幸一 )
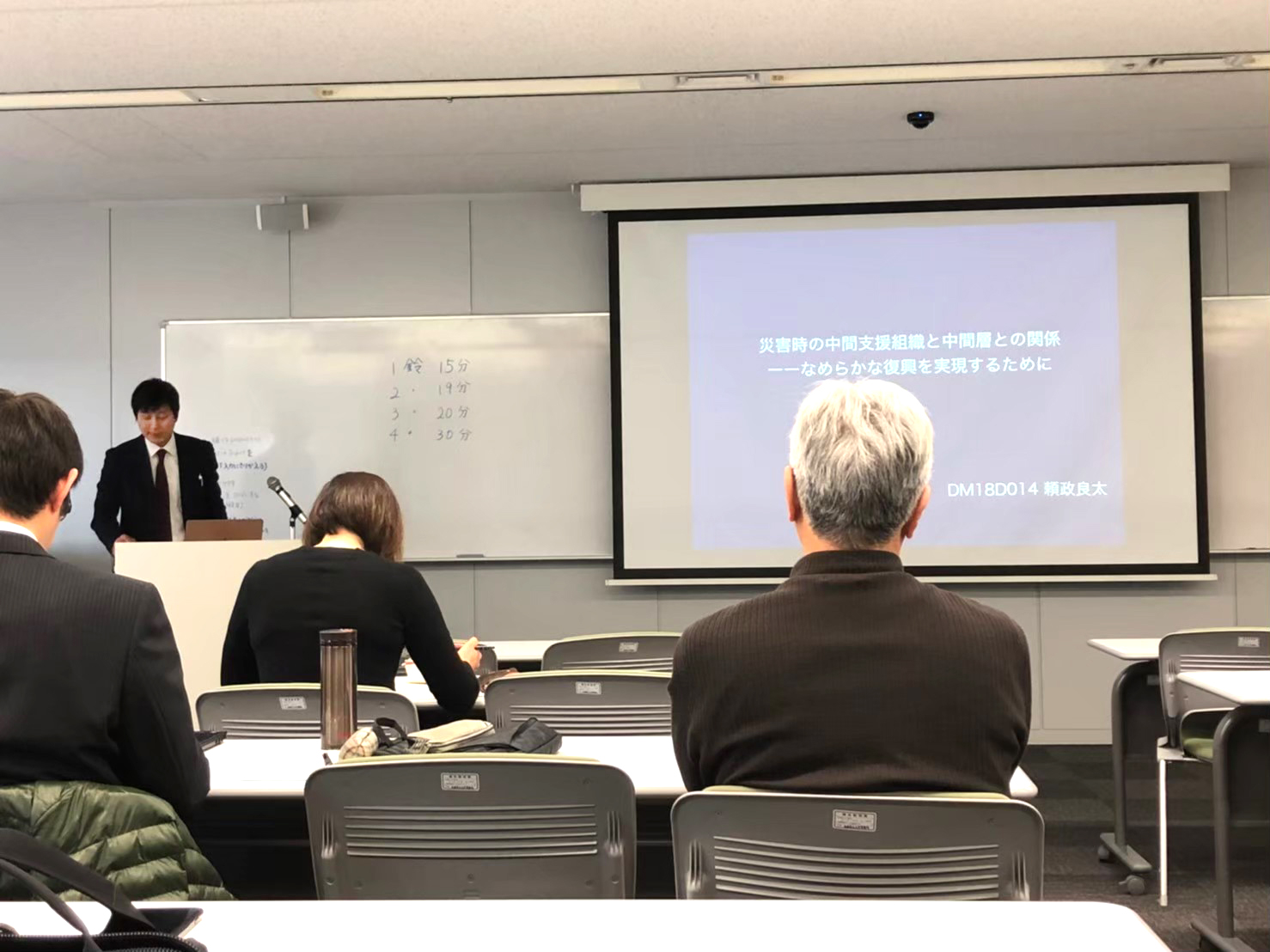
大学院にて、修士論文を発表中の頼政さん

被災者支援の研究として、大学院の同級生と被災地で活動しているNPO法人の方にヒアリング