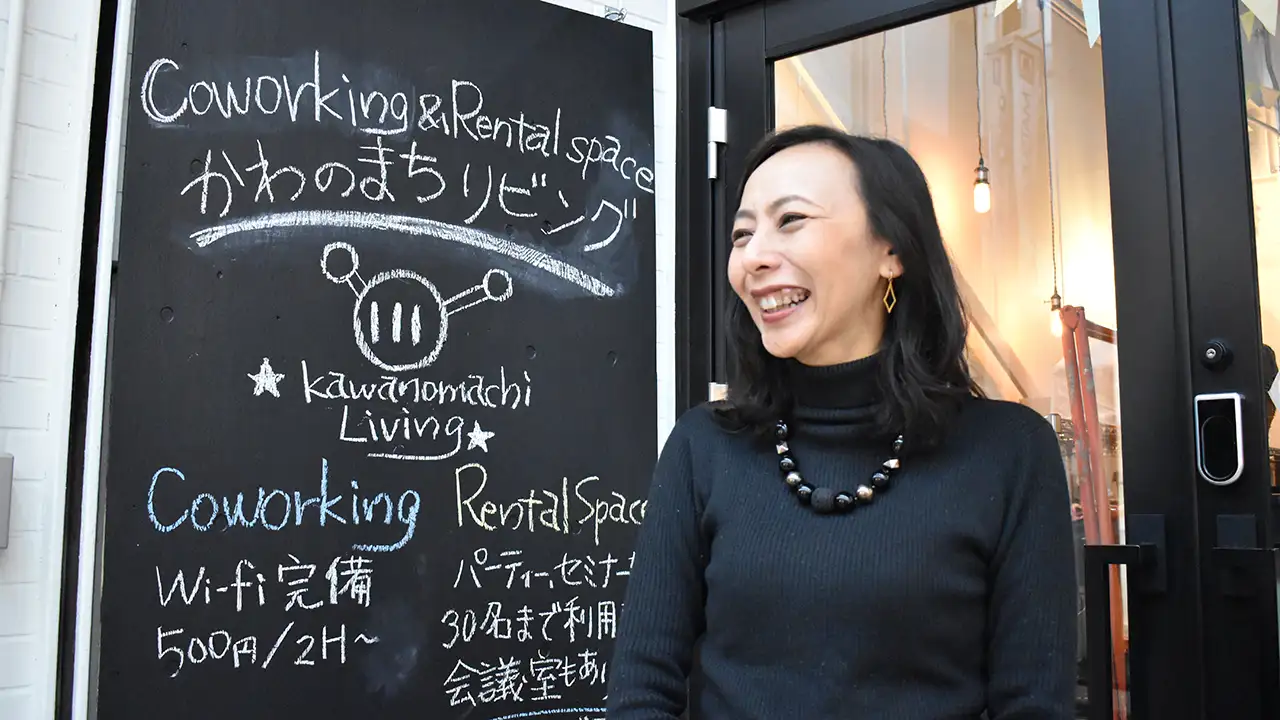中西和也さんの生き方は、自然体だ。「ひょうひょうとしていたい。」と話す一方で、「中途半端に終わらせるわけにはいかない。」と口にする、地域づくりへの確かな想い。2013年の取材から10年を経た今、活動と中西さん自身の現在について話を聴いた。
止まらない人口減少に見出した「希望」
今年の春、家島の中学校を、ある一人の生徒が卒業した。
「学校に通うことが少ししんどくなっていた子どもが、家族旅行に訪れたこの島で、心が軽くなったと喜んだそうです。それをきっかけに、家島中学への転校を切望され、父親を地元に残し母子で家島に転居。二拠点生活を続けながら通学され、卒業と同時に地元へ帰られました。」
かつて荒天時の避難港として栄えた家島。今度は、現代社会に生きづらさを抱える子どもや大人の「心の避難港」になれないか。中学生を受け入れた今回の事例を新たな事業に発展させるべく、中西さんは模索を始めている。
「私自身が、一般的な社会生活の枠組みに収まっていませんから(笑)。本当は働きたくないですし、今も働いている実感はあまりありません。」と、屈託のない笑顔を見せる中西さん。
実は、子どもの頃から働くことへの違和感を覚えていた。


働くって、楽しくないの?
「死にそうな顔をして、生きている――。」
塾に通う夏休みの朝の満員電車。疲れた様子で通勤する大人たちの様子を目にし、当時、小学生だった中西さんは、「仕事って何だろう。」と考えるようになった。疑問を抱えたまま、建築士を志した学生時代には、自らが理想とする暮らしありきの建築と、商売として売れるものを建てる現実のずれを受け入れられず、経済活動に「憎悪」さえ覚えるようになった。
そんな中西さんが「納得のいく働き方ができる場所かもしれない。」と感じたのが家島だった。
心惹かれた家島が抱える、人口減少という地域課題に立ち向かうため島に移住。ボランティア主体に続けてきた活動が10年を過ぎようとする2020年、転機が訪れる。経営していた島内のカフェに、シェフを雇用しようとしたことがきっかけだった。



「まちづくりで、お金を稼ごう」
「趣味は魚釣りです!」
オンライン画面の向こうで、明るい声が弾む。シェフの募集に応募してきた人物だ。島暮らしに憧れて連絡したものの、移住が現実味を帯び出すと音信不通になってしまう応募者も多い中、島への移住を条件にした転職のハードルも軽々と超えてきた。
以来、およそ2年。中西さんが感心するのは、カフェを訪れる観光客への誠実な対応ぶりだ。島の魚釣りスポットの話で盛り上がり、釣れる魚の情報を語り尽くす。時には、島の祭りの魅力を観光客と語り合うなど、仕事も暮らしも楽しんでいるようだ。
社員という形で、家島に住む人を増やすことができた。わずかな人数だけれど、家島に住む人間として、できる範囲で地域課題の解消に貢献できた。そして何より、彼の姿を目にするうちに、「島に住み、島での暮らしを楽しめる人を増やしたい」と改めて強く思った。
そして、中西さんは気が付いた。
「自分が売上を伸ばして事業を育て、島へ移住して働いてくれる社員を増やせばいいんだ。」
抱いていた経済活動への負のイメージを払しょくできず、営利事業として地域づくりに取り組むことに積極的になれなかった中西さんに、変化が生まれた。
いい車に乗りたいわけじゃない。いい家に住みたいといった欲もない。多くを稼ぎたいとも思わない。しかし、人生をかけて島へ移住し、就職してくれる社員には、ちゃんと給料を出さなくてはいけないし、できれば少しでも多く渡したい。
「社員のために、家島のために、事業としてきちんと売上を上げよう。」
対価を受け取ることへの後ろめたさが、ようやく吹っ切れた。
「今、建築士の友だちと一緒に、島での仕事をつくっているんです。」
島に増える空き家をリノベーションし、宿泊施設を増やそうという事業が進行している。すでにオープンしている一棟貸の宿泊施設は、宿泊マネージャーも新たに採用し順調に稼働中だ。
いずれは、家島で元気を取り戻した中学生のように、社会生活に生きづらさを抱える人たちが、移住できる環境を整えたい。もちろん営利事業として、取り組むつもりだ。



ありのままの暮らしを守る、それが地域づくり
「地域づくりとは、地域にある『暮らし』を守ること」と語る中西さん。
「理想的な地域の在り方は、それぞれの地域に、それぞれの暮らしがあること。例えば、『死んだ魚は猫も食わない』と言われるほど、新鮮な魚を食べることができる家島のような、その地域の働き方も生き方も、生活している人も、ありのままにある暮らしです。それぞれの地域の在り方が違えば、自分に合う地域や場所、働き方の選択肢も増える。自分に合った在り方を選ぶことができれば、誰もが自分らしく生きられるはずです。」
家島へ移住したばかりの中西さんを、「食べていけるの?」と心配し、アルバイトを紹介してくれた人。地域づくりの実績もなかった当初から「話を聴いてやろう」と応援してくれた人。家島の温かい人々への感謝の気持ちと共に、活動を続ける中西さんにとって、家島は「人生を賭した社会実験の場」だと言う。
「俯瞰的に眺めれば、ひとりの若者が移住し、様々な経験をしながら事業をしている場所。一つひとつを見れば、空き家の改修や利活用、社会福祉的な事業をどう形にするか。家島の人たちも望んでいるように、今の島での暮らしを守り、最終的には日本全国へ広げたい。隣の島へ行けば、全く違う働き方があり、少し離れた地域を訪れれば、異なった生活様式がある。それが全国に広がっていることが、日本の魅力でもありますから。」
「島の人たちとの会議では、一杯酌み交わしながら話し込むこともあります。どこまでが仕事時間で、どこからか趣味なのかわからない。」と笑う中西さん。家島は、求め続けた働き方を形にできるフィールドだった。
「この暮らしを選んでよかった。」
中西さんは今、働くことを楽しんでいる。